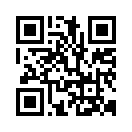2016年04月11日
やる気のない子はほっとく
恵まれている子が塾に行くのを嫌がったりする。
親が塾に相談に来て
「先生ウチの子どもが勉強を嫌がるんです。
やる気を出させるにはどうすれば」と相談に来る
「ほっとけばよい」答える。
世界を見よ、東南アジアの子を見よ、
沖縄の普通の末端を見よ。塾に行きたくてもいけない子、
腹空いて学校さえまともにいけない子がどれほどいるか
見て聞いて考えてみてください」
母「まあひどい!
それじゃうちの子に勉強するなというのですか」
先生「ほっとけばよいと言っているのです。
あなたこそ家事以外に1日3時間勉強してみてください。
きっと子どもが変わります」
なんて言ってみたいが、なかなか ^_^;
………………………………………………………
砂川よしひろ(沖縄県浦添市在)
教育アドバイサー 子育て・学習支援
企画編集者(自分史 地域史 社史の制作)
コピーライティング 人生コーチング
090-4981-8723 sunayoshi222@softbank.ne.jp
………………………………………………………
親が塾に相談に来て
「先生ウチの子どもが勉強を嫌がるんです。
やる気を出させるにはどうすれば」と相談に来る
「ほっとけばよい」答える。
世界を見よ、東南アジアの子を見よ、
沖縄の普通の末端を見よ。塾に行きたくてもいけない子、
腹空いて学校さえまともにいけない子がどれほどいるか
見て聞いて考えてみてください」
母「まあひどい!
それじゃうちの子に勉強するなというのですか」
先生「ほっとけばよいと言っているのです。
あなたこそ家事以外に1日3時間勉強してみてください。
きっと子どもが変わります」
なんて言ってみたいが、なかなか ^_^;
………………………………………………………
砂川よしひろ(沖縄県浦添市在)
教育アドバイサー 子育て・学習支援
企画編集者(自分史 地域史 社史の制作)
コピーライティング 人生コーチング
090-4981-8723 sunayoshi222@softbank.ne.jp
………………………………………………………
2016年04月09日
日本の若者に向けたムヒカ氏の言葉
「世界でいちばん貧しい大統領」ムヒカ氏
「発展ではなく幸福のために私達はいる」

「生きる」と言うことは間違え、失敗する事であり、
それらから学ぶこと。
昼下がりのキャンパスに300人以上の学生と多くの市民が集まりました。ウルグアイの前大統領、ホセ・ムヒカ氏の講演を聞くためです。
ホセ・ムヒカ前大統領は、その質素な暮らしぶりから「世界でいちばん貧しい大統領」として知られ、2012年にブラジルのリオで行われた国連会議でのスピーチでは「世界が抱える諸問題の根源は、我々の生き方そのものにある」と説いて、世界にその名が知られるようになりました。
そんなムヒカ氏が先日、書籍『ホセ・ムヒカ 世界でいちばん貧しい大統領』(角川文庫)の発売を記念して初来日を果たし、東京外国語大学(東京都府中市)で講演会を行いました。
80歳を迎えたムヒカ氏が、真剣な眼差しで聞き入る学生たちに語ったのは「世界を変えるために戦った経験から得られた4つの教訓」です。以下、日本の若者に向けたムヒカ氏の言葉をまとめました。
1. 消費主義に支配されるな
現代の消費主義に支配されてはいけません。でもこれは、言うのは簡単です。消費主義は、蜘蛛の巣に引っかかるようなものです。企業はこれを買え、あれを買えとあなたにお金を使うように仕向けてきます。それに甘んじてモノを買い続ければ、あなたはもっとお金を稼ぐために、もっと長い時間を、お金を稼ぐために費やすことになるでしょう。そうなると、あなたの自由な時間はどんどん減ってしまいます。
本当に必要なものだけを買うようにしてください。そうすれば、あなたの自由な時間はもっと増えます。貧乏とは、多くのものを必要だと思ってしまう心のことです。無限にモノをほしがってしまう欲こそが「貧しい」ということなのです。
2. 歩き続けよ
人生でもっとも重要なことは、勝つことではありません。歩き続けることです。それはつまり、転んでも毎回起き上がること、新たに何かを始める勇気を持つということ、何かに打ち負かされたときにまた立ち上がるということです。
私は若い時、世界を変えるために戦いましたが、残念ながら世界を変えることはできませんでした。そして私は牢獄に入れられて10年以上を過ごしました。これは私にとって非常につらい時でした。でも、その辛い時間がなかったら、今の自分はなかったと思っています。
3. 同じ志を持つ仲間を見つけて闘争せよ
社会は集団というツールがないと変わりません。もしあなたが今の現状に不満を持っているなら、同じように不満を持っている人を見つけて仲間にしてください。仲間を集めて集団を作って主張すれば、大きな力はなくても、社会に意識を植えつけることができます。
これまでも、社会はこうして少しずつ変化してきました。100年も前は、労働者は15時間も18時間も長時間の労働をするのが当たり前でした。そんなとき、ある人がこんなことを言い出したのです。「1日の労働時間が8時間にして、寝る時間は8時間必要で、それ以外のプライベートな時間が8時間は必要だ」と。当時の人々の多くは「コイツはなんて頭のおかしいことを言うんだ」と思ったことでしょう。
でも、その人は仲間を集めて、闘争を始めたのです。今では8時間労働が当たり前になっていますが、自由な時間のために戦った人がいるのです。今ではそんな闘争をした人は忘れ去られているのかもしれませんが、彼らは闘争することで他の人の意識を変えたのです。
社会が変わり続ければ、1日の労働時間は4時間が当たり前になることも十分起こりうることです。
日本では、人々があまり希望が持てないと聞きました。若者の多くが投票にいかないそうですね。彼らは、社会が変化するということを信じていないのでしょう。
何か魔法のようなものが社会を変えてくれると考えないでください。あなたと同じ志を持つ人はたくさんいます。仲間を見つけて集まってください。そして、戦ってください。
4. 自分の利己主義を抑え
私は「最後の審判」を信じていません。でも何らかの人生の時点で、鏡の前に立ち止まって自分自身を見つめるときが来ることはあると思っています。そんなとき、これまで何かをやろうとして、何度も失敗したけど、行動に移した数々のことを思い出すかもしれません。「100やりたかったことがあるとすれば、5しかできなかったけど、行動に移すことができて有意義だった」と思えるかもしれません。
でも反対に、「私は人生で何もしてこなかった」「私の人生は浪費の連続だった」、「誰に対しても、手を差し伸べなかった」、「誰かのために時間を費やすことなんてなかった」と思うこともあるかもしれません。そんな人は、鏡の前に立ち止まったとき、自分の姿を見て失望するでしょう。そこに映っているのは、自分のエゴイズムでしかないからです。
すべての生命はエゴイズム(利己主義)を持っています。それは自分自身を守るために、自然が私たちに与えてくれたものです。でも、人間はひとりでは生きていけません。必ず他者を必要とする生き物なのです。
他人に勝つために戦うのはやめてください。そうではなくて、自分自身の心の中にあるもののために戦うのです。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
講演や質疑応答の間、ムヒカ氏が何度も繰り返していたのは「闘争せよ」という言葉でした。「闘争を生まないことが理想だ」と教えられてきた人にとって、この言葉には抵抗感があるかもしれません。でも、ムヒカ氏はこう続けます。
あなたが生きている限り、他者との衝突は避けられません。大事なのは、コンフリクトを起こさないことではなく、どうやってコンフリクトを解決していくかということです。
あなたが闘争しないと社会は変わっていかない。ムヒカ氏のメッセージは、平和すぎる日本に向けられた警鐘なのかもしれません。
………………………………………………………
砂川よしひろ(沖縄県浦添市在)
教育アドバイサー 子育て・学習支援
企画編集者(自分史 地域史 社史の制作)
コピーライティング 人生コーチング
090-4981-8723 sunayoshi222@softbank.ne.jp
………………………………………………………
「発展ではなく幸福のために私達はいる」

「生きる」と言うことは間違え、失敗する事であり、
それらから学ぶこと。
昼下がりのキャンパスに300人以上の学生と多くの市民が集まりました。ウルグアイの前大統領、ホセ・ムヒカ氏の講演を聞くためです。
ホセ・ムヒカ前大統領は、その質素な暮らしぶりから「世界でいちばん貧しい大統領」として知られ、2012年にブラジルのリオで行われた国連会議でのスピーチでは「世界が抱える諸問題の根源は、我々の生き方そのものにある」と説いて、世界にその名が知られるようになりました。
そんなムヒカ氏が先日、書籍『ホセ・ムヒカ 世界でいちばん貧しい大統領』(角川文庫)の発売を記念して初来日を果たし、東京外国語大学(東京都府中市)で講演会を行いました。
80歳を迎えたムヒカ氏が、真剣な眼差しで聞き入る学生たちに語ったのは「世界を変えるために戦った経験から得られた4つの教訓」です。以下、日本の若者に向けたムヒカ氏の言葉をまとめました。
1. 消費主義に支配されるな
現代の消費主義に支配されてはいけません。でもこれは、言うのは簡単です。消費主義は、蜘蛛の巣に引っかかるようなものです。企業はこれを買え、あれを買えとあなたにお金を使うように仕向けてきます。それに甘んじてモノを買い続ければ、あなたはもっとお金を稼ぐために、もっと長い時間を、お金を稼ぐために費やすことになるでしょう。そうなると、あなたの自由な時間はどんどん減ってしまいます。
本当に必要なものだけを買うようにしてください。そうすれば、あなたの自由な時間はもっと増えます。貧乏とは、多くのものを必要だと思ってしまう心のことです。無限にモノをほしがってしまう欲こそが「貧しい」ということなのです。
2. 歩き続けよ
人生でもっとも重要なことは、勝つことではありません。歩き続けることです。それはつまり、転んでも毎回起き上がること、新たに何かを始める勇気を持つということ、何かに打ち負かされたときにまた立ち上がるということです。
私は若い時、世界を変えるために戦いましたが、残念ながら世界を変えることはできませんでした。そして私は牢獄に入れられて10年以上を過ごしました。これは私にとって非常につらい時でした。でも、その辛い時間がなかったら、今の自分はなかったと思っています。
3. 同じ志を持つ仲間を見つけて闘争せよ
社会は集団というツールがないと変わりません。もしあなたが今の現状に不満を持っているなら、同じように不満を持っている人を見つけて仲間にしてください。仲間を集めて集団を作って主張すれば、大きな力はなくても、社会に意識を植えつけることができます。
これまでも、社会はこうして少しずつ変化してきました。100年も前は、労働者は15時間も18時間も長時間の労働をするのが当たり前でした。そんなとき、ある人がこんなことを言い出したのです。「1日の労働時間が8時間にして、寝る時間は8時間必要で、それ以外のプライベートな時間が8時間は必要だ」と。当時の人々の多くは「コイツはなんて頭のおかしいことを言うんだ」と思ったことでしょう。
でも、その人は仲間を集めて、闘争を始めたのです。今では8時間労働が当たり前になっていますが、自由な時間のために戦った人がいるのです。今ではそんな闘争をした人は忘れ去られているのかもしれませんが、彼らは闘争することで他の人の意識を変えたのです。
社会が変わり続ければ、1日の労働時間は4時間が当たり前になることも十分起こりうることです。
日本では、人々があまり希望が持てないと聞きました。若者の多くが投票にいかないそうですね。彼らは、社会が変化するということを信じていないのでしょう。
何か魔法のようなものが社会を変えてくれると考えないでください。あなたと同じ志を持つ人はたくさんいます。仲間を見つけて集まってください。そして、戦ってください。
4. 自分の利己主義を抑え
私は「最後の審判」を信じていません。でも何らかの人生の時点で、鏡の前に立ち止まって自分自身を見つめるときが来ることはあると思っています。そんなとき、これまで何かをやろうとして、何度も失敗したけど、行動に移した数々のことを思い出すかもしれません。「100やりたかったことがあるとすれば、5しかできなかったけど、行動に移すことができて有意義だった」と思えるかもしれません。
でも反対に、「私は人生で何もしてこなかった」「私の人生は浪費の連続だった」、「誰に対しても、手を差し伸べなかった」、「誰かのために時間を費やすことなんてなかった」と思うこともあるかもしれません。そんな人は、鏡の前に立ち止まったとき、自分の姿を見て失望するでしょう。そこに映っているのは、自分のエゴイズムでしかないからです。
すべての生命はエゴイズム(利己主義)を持っています。それは自分自身を守るために、自然が私たちに与えてくれたものです。でも、人間はひとりでは生きていけません。必ず他者を必要とする生き物なのです。
他人に勝つために戦うのはやめてください。そうではなくて、自分自身の心の中にあるもののために戦うのです。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
講演や質疑応答の間、ムヒカ氏が何度も繰り返していたのは「闘争せよ」という言葉でした。「闘争を生まないことが理想だ」と教えられてきた人にとって、この言葉には抵抗感があるかもしれません。でも、ムヒカ氏はこう続けます。
あなたが生きている限り、他者との衝突は避けられません。大事なのは、コンフリクトを起こさないことではなく、どうやってコンフリクトを解決していくかということです。
あなたが闘争しないと社会は変わっていかない。ムヒカ氏のメッセージは、平和すぎる日本に向けられた警鐘なのかもしれません。
………………………………………………………
砂川よしひろ(沖縄県浦添市在)
教育アドバイサー 子育て・学習支援
企画編集者(自分史 地域史 社史の制作)
コピーライティング 人生コーチング
090-4981-8723 sunayoshi222@softbank.ne.jp
………………………………………………………
2016年04月08日
心理学者アドラーの名言12
心理学者アドラーの名言100より12に絞りました
(教育に関すること・最重要なこと砂川の編集抜粋)
1.叱られたり、ほめられたりして育った人は、叱られたり、ほめられたりしないと
行動しなくなる。そして、評価してくれない相手を、敵だと思うようになるのだ。
2.「よくできたね」とほめるのではない。「ありがとう、助かったよ」と感謝を伝える。
3.すべての悩みは対人関係の課題である。仙人のような世捨て人でさえも、
実は他人の目を気にしているのだ。
4.ほめてはいけない。ほめることは「あなたは私よりも下の存在だ」
「どうせあなたにはできっこない」と相手に伝えることに等しいからだ
5.「この子は言葉を覚えるのが遅いので・・・・」と母親が子どもの通訳を買って出る。
すると子どもは、自分で話す必要がなくなり、本当に言葉が遅くなるだろう。
6.罰を与えるのではない。結末を体験させるのだ。子どもが食事の時間になっても
帰ってこなければ、一切叱らずに食事を出さなければよい。
7.問題行動に注目すると人はその問題行動を繰り返す。
叱ることは、悪い習慣を身につけさせる最高のトレーニングなのだ。
8.健全な人は、相手を変えようとせず自分がかわる。不健全な人は、相手を操作する。
9.強制を辞める。相手に自分で決めさせる。自分を信じ他人を信じ居場所を見つける。
10.あらゆる人間関係のトラブル原因は他人の課題に土足で踏み込む、から。
11.自分の課題とは「その問題を放置した場合、不利益を被るのは誰か?」で考える。
12.自分と他者との「課題の分離」が出来るようになるとシアワセの第一歩である。
(教育に関すること・最重要なこと砂川の編集抜粋)
1.叱られたり、ほめられたりして育った人は、叱られたり、ほめられたりしないと
行動しなくなる。そして、評価してくれない相手を、敵だと思うようになるのだ。
2.「よくできたね」とほめるのではない。「ありがとう、助かったよ」と感謝を伝える。
3.すべての悩みは対人関係の課題である。仙人のような世捨て人でさえも、
実は他人の目を気にしているのだ。
4.ほめてはいけない。ほめることは「あなたは私よりも下の存在だ」
「どうせあなたにはできっこない」と相手に伝えることに等しいからだ
5.「この子は言葉を覚えるのが遅いので・・・・」と母親が子どもの通訳を買って出る。
すると子どもは、自分で話す必要がなくなり、本当に言葉が遅くなるだろう。
6.罰を与えるのではない。結末を体験させるのだ。子どもが食事の時間になっても
帰ってこなければ、一切叱らずに食事を出さなければよい。
7.問題行動に注目すると人はその問題行動を繰り返す。
叱ることは、悪い習慣を身につけさせる最高のトレーニングなのだ。
8.健全な人は、相手を変えようとせず自分がかわる。不健全な人は、相手を操作する。
9.強制を辞める。相手に自分で決めさせる。自分を信じ他人を信じ居場所を見つける。
10.あらゆる人間関係のトラブル原因は他人の課題に土足で踏み込む、から。
11.自分の課題とは「その問題を放置した場合、不利益を被るのは誰か?」で考える。
12.自分と他者との「課題の分離」が出来るようになるとシアワセの第一歩である。
2016年04月08日
子どもを将来、国立大学へ行かせるのに必要なこと
あなたの子どもを国立大学など
いわゆるいいところに行かせたいなら
小学6年に上がるまでにさせておく
「6つのこと」
中学へ上がってからでは遅いです。
中学の学習は小学5・6年の応用問題です。
作文・基礎計算は小5で完成されます。
次に述べる(1)~(6)はすべて
小学6年までに(難関目指すなら5年)という
冠詞がつきます。
(1)ものを読む力・読書習慣を身につけさせる
~6年までの漢字で新聞は読める・主述の識別~
(2)健康な体力~個人差はあれど明るく元気に
~スポーツで忍耐力・集中力をつけさせる~
(3)礼節があり人前で話・意見が言える
~好きな物などの説明ができる・明るい~
(4)割合(パーセント・歩合)の計算ができる
~30%OFFは×0.7 4打数1安打は2割5分~
5年の算数である 暗算で答える
5)都道府県の所在地や特徴を理解している
~野球やサッカーチームの所在地からでも~
ヨーロッパ・アジアにも詳しい
6)周りの現象に関心があり家の手伝いができる
~夏のキャンプなど自然体験も経験させる~
「天気と電気」は日常話題程度の知識がある
遠い記憶~那覇市栄町の大道小学校時代の私~
私の小学校時代、家の机で勉強した記憶がほとんどありません。
五人兄弟の末っ子にはお下がりの古い小さな座卓だけでした。
そんな環境でも上記の(1)~(6)は習得していました。
少年野球・子ども会のリーダーだったので外での活動ばかり。
野球は大好きで甲子園出場全校は毎年くわしく覚えていました。
好きなプロ野球選手の打率勝率は普通に頭に入っていました。
新聞は毎朝兄たちと奪い合いながら読んでいました。
学校図書館の本は無料なのでありがたく借りて読んでいました。
学校職員だった母は毎週末「政治運動」に参加していたので
小学生時分から民主主義や憲法に関心を示していました。
いま小6が使っているアドバンス教材5・6年用
それだけで高校入試の理科・社会が8割解けます。
つまり中3標準以上のレベルまで上げられるのです。
なにが言いたいか。
小5~小6でたいていのことは決まっている。
親のみなさんも自分が6年生の頃を思いだしてください。
周りの友だちを。国立大学に行ける子、医者になる子
学校の先生になる子 政治家になる子 ふつうの子
危ない人生を歩む子… だいたい決まってませんでしたか?
小学生までに 特に小5で上の6項目が習得できるような
そういう環境をつくってあげましょう!
………………………………………………………
砂川よしひろ(沖縄県浦添市在)
教育アドバイサー 子育て・学習支援
企画編集者(自分史 地域史 社史の制作)
コピーライティング 人生コーチング
090-4981-8723 sunayoshi222@softbank.ne.jp
………………………………………………………
いわゆるいいところに行かせたいなら
小学6年に上がるまでにさせておく
「6つのこと」
中学へ上がってからでは遅いです。
中学の学習は小学5・6年の応用問題です。
作文・基礎計算は小5で完成されます。
次に述べる(1)~(6)はすべて
小学6年までに(難関目指すなら5年)という
冠詞がつきます。
(1)ものを読む力・読書習慣を身につけさせる
~6年までの漢字で新聞は読める・主述の識別~
(2)健康な体力~個人差はあれど明るく元気に
~スポーツで忍耐力・集中力をつけさせる~
(3)礼節があり人前で話・意見が言える
~好きな物などの説明ができる・明るい~
(4)割合(パーセント・歩合)の計算ができる
~30%OFFは×0.7 4打数1安打は2割5分~
5年の算数である 暗算で答える
5)都道府県の所在地や特徴を理解している
~野球やサッカーチームの所在地からでも~
ヨーロッパ・アジアにも詳しい
6)周りの現象に関心があり家の手伝いができる
~夏のキャンプなど自然体験も経験させる~
「天気と電気」は日常話題程度の知識がある
遠い記憶~那覇市栄町の大道小学校時代の私~
私の小学校時代、家の机で勉強した記憶がほとんどありません。
五人兄弟の末っ子にはお下がりの古い小さな座卓だけでした。
そんな環境でも上記の(1)~(6)は習得していました。
少年野球・子ども会のリーダーだったので外での活動ばかり。
野球は大好きで甲子園出場全校は毎年くわしく覚えていました。
好きなプロ野球選手の打率勝率は普通に頭に入っていました。
新聞は毎朝兄たちと奪い合いながら読んでいました。
学校図書館の本は無料なのでありがたく借りて読んでいました。
学校職員だった母は毎週末「政治運動」に参加していたので
小学生時分から民主主義や憲法に関心を示していました。
いま小6が使っているアドバンス教材5・6年用
それだけで高校入試の理科・社会が8割解けます。
つまり中3標準以上のレベルまで上げられるのです。
なにが言いたいか。
小5~小6でたいていのことは決まっている。
親のみなさんも自分が6年生の頃を思いだしてください。
周りの友だちを。国立大学に行ける子、医者になる子
学校の先生になる子 政治家になる子 ふつうの子
危ない人生を歩む子… だいたい決まってませんでしたか?
小学生までに 特に小5で上の6項目が習得できるような
そういう環境をつくってあげましょう!
………………………………………………………
砂川よしひろ(沖縄県浦添市在)
教育アドバイサー 子育て・学習支援
企画編集者(自分史 地域史 社史の制作)
コピーライティング 人生コーチング
090-4981-8723 sunayoshi222@softbank.ne.jp
………………………………………………………
2016年04月07日
7つの習慣 まとめ
パラダイムと原則について
・パラダイム(世界を見る見方、地図、レンズ)認識、理解、解釈を決めるもの
今までの経験がパラダイムを決めている
世界をあるがままに見ているのではなく、自分たちがあるがままに見ている
見方が変われば、あり方が変わる
レンズや地図は主観的事実、客観的事実は原則からなる
・パラダイム転換(あるひとつのものの見方が別の見方へ移行すること)
・原則は深い基礎的な真理
・インサイド・アウト(内から外へ)、自分自身の内面(インサイド)
・習慣の要素
個性主義 (テクニック) 上辺だけの問題に対応 表面的な成功 二次的なもの
人格主義 (根本な土台) 人格に深く内面な対応 真の成功 一次的なもの
知識(何をするか、なぜするか)
スキル(どうやってするか)
やる気(実行したい気持ち)
●第一部 私的成功
○第1の習慣
主体性を発揮する
・多くの人は社会の鏡(社会の通念、人々の考え)からパラダイムや考えを得ている
・人間は刺激と反応の間に選択の自由がある
自分の反応を選択する能力
主体性をもつ=自分の人生に責任をとる
反応的 周りの物的な環境に大きく影響を受ける
主体的 自分の価値観に基づき率先力を持って行動
・自分の身に何かが起こるのではなく、それにどう反応するかが重要
率先力 自分から進んで状況を改善する行動を起こすこと
関心の輪 関心を持っている事柄
影響の輪 関心を持っている事柄であり
直接コントロールできるもの
・直面する3種類の問題
直接的にコントロールできる問題(自分の行動と関係している問題)
間接的にコントロールあるいは影響できる問題(他人の行動と関係している問題)
全くコントロールできない問題(誰も影響できない問題、過去の出来事)
・問題は自分の外にあると考えることが問題である(他人のせいにしない)
・結果は選択できないため、間違いは修正しなくてはならない
・目標を設定し行動、自分自身に約束をして守る
・主体性を発揮するの応用
①自分自身と周りの人々の反応的な言葉を2日間聞いてみる
②近い将来、直面するであろう状況、反応的になることを過去の経験からひとつ選んで影響の輪を考慮して主体的な反応を示すためにでき
ることを考えてみる。そして、主体的に反応している自分の姿、行動をイメージして刺激と反応の間のを思い起こし、選択の自由を活用す
る約束を自分自身にする
③仕事や私生活で抱えている問題をひとつ選択する。それが直接的か間接的かあるいは全くコントロールできない問題にあたるか考える。
その問題を解決するために自分の影響の輪の中でとれる具体的な行動を打ち出して実行する
④主体性の30日間のテスト(目標を設定し行動、自分自身に約束をして守る)を実行する。影響の輪の変化を意識してみる。
○第2の習慣
目的を持って始める
・目的を持って始めるということはすべての行動を測るための尺度として人生最後の姿(自分の葬式、友人や家族、知人になんて言ってもら
いたいか)を描き、それを念頭において今日という1日を始めること
・目的を持って始めるということは人生のはしごの掛け違いをなくす
・すべてのものは2度つくられる
知的な第1の創造 設計図、計画、脚本 第2の習慣
物的な第2の創造 物の組み立て、実行 第3の習慣
・第2の習慣は自己リーダーシップの原則に基づいている
リーダーシップとは正しい方向に導くこと、マネジメントは物事を正しく行うこと
・ミッション・ステートメント(個人的な憲法、信条)
自分はどうなりたいのか、何をしたいのか、自分の行動の基礎となる価値観、原則明らかにする
・原則中心の生活をすることで安定性、方向性、知恵ならびに力が発揮される
・視野を広げてイメージ化、自己宣言を書く
・自己宣言は個人的、積極的、現在進行形、イメージ化できる、感情を表すの5つの要素
(例)子供たちが悪いことをするとき、私(個)は知恵・愛ある態度(積)で対応する(現)ことに深い満足感(感情)を覚える(イ)
・役割(生活上の各領域)と目標
・目的を持って始めるの応用
①葬式のイメージ化をして、家族、友人、仕事、社会、地域などの人格、貢献、達成したことなどを経験して思いを記録する
②自分の生活における役割を書いてバランスに満足しているか考える
③個人的なミッション・ステートメントを書き始める時間をスケジュールにいれる
④自分の今の中心においているものを考えて生活のパターンが望ましいものか考える
⑤個人的なミッション・ステートメントを作成するのに役立つアイデアや引用文を集める
⑥近い将来直面するプロジェクトのひとつを取り上げて知的創造の原則を活用してみる。望んでいる結果とそれを作り出すのに必要な行動
・手順を書いてみる
⑦原則を家族や職場の人と分かち合い、家族や職場のミッション・ステートメントを作るプロセスを開始する。
○第3の習慣
重要事項を優先する
・活動を定義するのは緊急度と重要度であり時間管理のマトリックスで表現できる
・第二領域に集中することで自己管理
・第三領域、第四領域にノーといえる大きなイエスが大切
第一領域 緊急で重要
第二領域 緊急でないが重要
第三領域 緊急で重要でない
第四領域 緊急でなく重要でない
・新しい時間管理(第二領域時間管理)ツールの6つの大切な特徴
①一貫性 自分のビジョン・ミッション、役割と目標、優先順位と計画を調和させられミッション・ステートメントを入れる場所が必要。
そして役割、目標を管理する場所も重要
②バランス 健康、家族、仕事、準備、自己啓発など大切な事柄が日々の生活で疎かにならないよう生活のぞれぞれの役割を管理できるよ
うになっていること
③第二領域の集中 週単位の計画で優先順位をスケジュールに入れる
④人間重視 大切な人間関係について考えてあるもの
⑤柔軟性 自分のスタイルやニーズにあうもの、やり方に柔軟に合わせられるもの
⑥携帯性 携帯するのに便利なもの
・第二領域に集中した計画の4つの基本的なステップ
①役割を定義する 生活の主な役割を考える
(例)夫、父親、商品開発者、研究員、部下を育てる者、友人、人生を楽しむ者、健康維持
②目標設定 次の1週間で各役割において達成したい目標を2~3つ設定する
(例)妻とコンサート、マーケット調査、夏期休暇の旅行計画
③スケジュール化 目標を念頭において特定の時間を割り当てる。 時間の余裕も残す
④日々の対応 日々の出来事によってスケジュールを変更させる。 優先順位をつける
長期的な計画 ミッション・ステートメント→役割→目標
1週間の計画 役割→目標→計画→実行、デレゲーション
・デレゲーション
デレゲーション 他の人に仕事を任せること
使い走りのデレゲーション(指示しないとできない)
完全なデレゲーション(指示なし、結果に焦点を合わせる、結果に責任を持たせる)
・完全なデレゲーション行うために
望む結果 出すべき結果に明確な相互理解を得る
ガイドライン 結果を出すにあたりルールがあれば明確に、少ない方がいい
使える資源 望む結果を出すために活用できる人的、金銭的、技術的、組織的な範囲
責任に対する報告 結果を評価する基準、評価する人、報告と評価、期限を具体的に
履行(不履行)の結果 評価の結果はどうなるか(賞罰)、金銭的な報酬など
・重要事項を優先するの応用
①自分の私生活、職場においてこれまで疎かにしていた第二領域の活動をひとつ打ち出す
②時間管理のマトリックスを書いて、それぞれの領域にどれぐらい時間を使っているか考える。それから3日間にわたり15分間隔で実際の時
間の使い方を記録する
③人に任せられそうなことをピックアップしてみる。そして任せる相手も書いてみる。デレゲーション、訓練のプロセスを開始するにはど
うすればいいか考える
④来週の計画を立てる。まず、その週の役割と目標を書き、具体的な行動計画に移す。1週間の終わりに計画が目標や価値観に反映されてい
たか評価する
⑤毎週、週単位の計画を立てる決意し、その計画を立てる時間をスケジュールに入れる
⑥自分の使っているツールを新しい時間管理ツールに切り替える。
●第ニ部 公的成功
信頼残高 ある関係において築かれた信頼のレベルを表すもの
礼儀正しい行動、親切、正直、約束で残高が貯まり、残高不足だと信頼関係が崩れていく
・信頼残高を作る6つの大切な預け入れ
①相手を理解する
相手にとって大切なことを、自分にとっても大切なことに思う必要がある
②小さいことを大切にする
小さな心遣いと礼儀は大切で、小さな無礼と不親切、無神経は大きな引き出しとなる
③約束を守る
約束を守ることは大きな預け入れであり、破ることは大きな引き出しである
④期待を明確にする
人間関係の問題は役割と目標を取り巻くあいまいな期待、お互いの期待像の相違
⑤誠実さを示す
個人的な堅実さが信頼を築き、様々な預け入れの基礎となる
誠実さを示す重要な方法のひとつは、その場にいない人に対して忠実になること
すべての人に対して平等に同じ原則に沿って接する
⑥引き出しをしてしまったときは誠意をもって謝る
間違いを犯すことはひとつの問題だがそれを認めないのはもっと大きな問題
愛の基礎的な法則 見返りを求めない無条件の愛
人生の基礎的な法則 協力、貢献、自制、誠実に沿って生活する
・Pの問題はPCの機会である
第4の習慣
Win-Winを考える
・人間関係の6つのパラダイム
①Win-Win
自分も勝ち、相手も勝つ。それぞれの当事者が欲しい結果を得ること
②Win-Lose
自分が勝ち、相手が負ける
③Lose-Win
自分が負けて、相手が勝つ
④Lose-Lose
自分も負けて、相手も負ける
⑤Win
自分だけの勝ちを考える
⑥Win-WinまたはNo Deal
Win-Winの合意または取引条件に至らなければ取引しないことに合意する
・Win-Winを支える5つの柱
①人格
・誠実、廉潔 自分自身に置く価値
・成熟 勇気と思いやりのバランス
勇気=自分の気持ちや信念を表現する、思いやり=相手の気持ちや信念を尊重する
・豊かさマインド すべての人を満足させることが可能であるというパラダイム
欠乏マインド 人生をゼロサムゲームとしてみている
②関係
・人格という土台上に立てられ維持されるもの、信頼残高こそがWin-Winの本質
③合意
・Win-Winの実行協定 5つの要素
望む結果 手段ではなく、何をいつまでに達成するか明確にする
ガイドライン 望む結果を達成するにあたり守るルール(原則、方針)を明確にする
使える資源 望む結果を達成ために活用できる人的、金銭的、技術的、組織的な範囲
責任に対する報告 評価基準、評価者および評価の時期を設定する
履行(不履行)の結果 プラス、マイナス自然・必然的な結果を設定、賞罰などを明確に
金銭的な報酬 給与、株、小遣い、罰金
心理的な報酬 評価、称賛、感謝、尊敬、信頼
与える範囲 研修、職場内訓練
与える責任の範囲 その人の権限の及ぶ範囲
④システム
・研修、計画立案、コミュニケーション、情報伝達、予算、報酬システムなど
⑤プロセス
・4つのステップ
1.問題を相手の立場から見る、相手を理解し、相手のニーズや心配や関心事を表現する
2.対処しなければならない課題や関心事(立場でない)を明確にする
3.完全に納得できる解決には、どういう結果を確保しないといけないか明確にする
4.その結果を達成するための新しい案や選択肢を打ち出す
・Win-Winを考えるの応用
①これから誰かと一緒に、合意にいたらなければならない状況、解決に向けて交渉しなければならい状況をひとつ選ぶ。その状況において勇気と思いやりのバランスを維持することを決意する
②自分の生活の中でWin-Winのパラダイムを妨げている要因や障害をリストアップする。この障害を取り除くために自分の影響の輪の中でなにができるだろうか考える。
③具体的にWin-Winの合意をつくりたい相手をひとり選ぶ。相手の立場に立って、相手の望んでいる結果を書いてみる。次に自分の観点から自分の望んでいるWinを確保するためにはどういう結果が必要なのか書いてみる。相手と話して、双方が満足する解決策を見つけるまでコミュニケーションを続ける用意があるか聞いてみる。
④自分の生活の中で重要な人間関係を3つ選ぶ。今の信頼残高はどれくらいあるだろうか、
その残高を増やすにはどんな預け入れができるかを書いてみる
⑤自分の今まで脚本づけ(Win-Loseなど)を考えてみる。その脚本づけが他の人と接し方にどういう影響を与えているか、その脚本のもととなっているのは何なのか、その脚本からつくられたパラダイムが自分が直面している現実に十分に対応できるものか検討する。
⑥難しい状況においても、相互利益を求める模範的な人を考えてみる。どうしたらこの人の模範をもっと身近に観察し、それから学べるかを考えてみる。
第5の習慣
理解してから理解される
・まず相手を理解するように努め、その後で自分を理解してもらう
・人生の最も大切なスキルはコミュニケーション(読む、書く、話す、聞く)
・4つのレベルで聞いている
①無視をする あるいは実際に聞いていない
②聞いたふりをする あいづちを打つという具合
③選択的に聞く 会話の部分部分しか耳に入れようとしない
④注意して聞く 注意深く集中して相手の言葉を聞くようになる
これよりも上の最も高い傾聴のレベルは感情移入の傾聴法
スキル中心な傾聴は基本的に自叙伝的な聞き方になっている
感情移入をして聞くことは相手の立場、見地から見ることで大きな預け入れになる
まず理解することが人生のあらゆる場面に作用する正しい原則
・4つの自叙伝的な反応と感情移入
①評価する 賛成、もしくは反対する
②探る 自分の視点から質問する
③助言する 自分の経験に基づき、助言やアドバイスを与える
④解釈する 自分の動機や行動をもとに相手の動機や行動を捉え、解釈、説明する
本当に理解したい気持ち、人格、相手との信頼残高、感情移入のスキルを身につけるまでは他の人の見地に立って、その人の見ている世界を見ることは絶対にできない
・感情移入の傾聴の4つの段階
①話の中身を繰り返す
(例)父さん、学校なんてもういやだよ⇒学校がいやなんだね
②話の中身を自分の言葉に置き換える
(例)父さん、学校なんてもういやだよ⇒そうか、学校に行きたくないんだ
③感情を反映する
(例)父さん、学校なんてもういやだよ⇒なんだかイライラしてるようだね
④話の中身を自分の言葉に置き換え、同時に感情を反映する(②+③)
(例)父さん、学校なんてもういやだよ⇒学校に行きたくなくて、なんだかイライラしてるようだね
・効果的に質問したり、助言を与えられる機会があったとしても、反応が感情的になるときには感情移入の傾聴に戻らなくてはならない
・たいていの場合は、人は外からの助言など必要ない。相手は本当に心の中を打ち明けることができれば、自分の問題を自分なりに整理し、その過程で解決策も明確になる
・一方で他の人の助言や協力が必要な場合がある。相手の利益を考え、感情移入の傾聴をし、相手の立場で問題を理解し、その解決策を一緒に探すこと
・エトス・パトス・ロゴス
エトス (人格) 個人の信頼性、信頼残高
パトス (人間関係) 感情移入、相手の感情的側面を理解する
ロゴス (理論展開) 理論、プレゼンテーションの論理展開
・手の目を通して人生を見つめることで、インサイド・アウトのアプローチにより影響の輪が広がり、関心の輪にあった様々な事柄に影響を及ぼす力ができる
・自叙伝を一度棚上げして、誠意をもって相手を理解する努力をしてみる
・理解してから理解されるの応用
①信頼残高が赤字になっている関係をひとつ考えてみる。相手の見地からその問題を理解しようとし、それを書き留める。次にその人と接するとき、理解を求めて聴くようにし、書き留めたことと聴いたことを比較する。自分の思い込んでたことと相手の立場や気持ちをどれぐらい理解していたか考える
②身近な人に感情移入、他人の話を真剣に聴くことを練習したい胸を伝え、1週間後にフィールドバックを求める。結果や気持ちを知る。
③他人のコミュニケーションを観察する機会があったら、耳をふさいで、目で見てみる。
言葉だけではわからない感情を読み取ってみる
④次回、不適切な自叙伝(探り、評価、助言、解釈)を挟んでいると気がついたら、その状況を預け入れに取り換えるために、それを認めて謝るようにする。「ごめんなさい。本当に理解しようとしていたのではないことに、今自分で気がつきました。もう一度最初から初めてもいいでしょうか」というように
⑤次にプレゼンテーションをするときに、それに感情移入に基づき行ってみる。相手の立場を相手以上に上手く説明してみる。それから自分の立場を相手の見地から説明し理解してもらう。
○第6の習慣
相乗効果を発揮する
・創造的な協力の原則
・相乗効果とは全体の合計が各部分の和より大きくなること
・第三案を探し、双方が満足する案を話し合いで導き出す
・違う意見を得ることこそが人間関係のもたらす利点
・相乗効果の本質は相違点、つまりは知的、情緒的、心理的な相違点を尊ぶこと
・すべての人は自分のあるがままに世界を見ていることを理解すること
・自分の物の見方に限界を認め、他の人のパラダイムと考え方に接する
・Win-Winの関係は信頼と協力が高い相乗効果的コミュニケーションがとれる
場の分析 駆動力と抑止力の均衡
現在得られている結果は均衡にある
駆動力 上向きの成長を促す
正の、合理的、論理的、意識的、経済的
抑止力 下向きの妨げを促す
負の、感情的、非論理的、無意識、社会的
・相乗効果を発揮するの応用
①自分と違った意見を頻繁に述べる人を考える。その相違点を、第三案を打ち出すたえの踏み台にする方法を考える。今自分が直面している問題やプロジェクトについて、その人の意見を求めるよにする。そして意見に価値を置き、それを真剣に受け止める。
②気に障る人をリストアップする。自分がより高いレベルの内面的安定を持ち、その相違点を尊ぶようにすることによって、彼らの持つ観点が相乗効果を生み出す原動力にならないか考える
③高いチームワークと相乗効果が欲しい状況を考えてみる。必要な相乗効果を支えるためには、どういう条件を整える必要があるか考える。また、そのために自分がなにができるのか考える
④今後、意見の相違やぶつかり合いが生じたとき、その人の立場を裏づける考えを理解しようとする。その人の意識している事柄を考慮に入れて、その問題を創造的かつ双方の利益になるような方法で解決していく。
●第三部 再新再生
○第7の習慣
刃を研ぐ
・バランスのとれた自己再新再生の原則
・肉体、精神、知性は毎日の私的成功
・再新再生の4つの側面
①肉体的側面(自制と責任感が強められる、第1の習慣)
・バランスのとれた栄養のある食事、十分な休養、定期的な運動
・運動 1週間のうち3~6時間、1日30分くらい目安
持久力 有酸素運動、心臓の能力向上(ジョギング、水泳など)
柔軟性 ストレッチング(有酸素運動の前後にウォーミングアップ、クールダウン)
強さ 筋肉に負かをかける運動(多少とりいれればいい筋肉トレーニング)
②精神的側面(自己リーダーシップが育成される、第2の習慣)
リラックスして精神を落ち着かせる、見つめ直す(祈り、瞑想など)
③知的側面(自己マネジメントを支えるもの、第3の習慣)
テレビは目的をもって見る、本を読む、文章を書くなど
④社会、情緒的側面(真の理解を深め、人の成功を喜ぶ、第4~6の習慣)
人の役に立つ貢献(ボランティア)
・組織の場合
①肉体的側面 ⇒経済的側面
②精神的側面 ⇒組織の目的、貢献の意味の発見
③知的側面 ⇒人の才能の開発、活用、評価
④社会、情緒的側面 ⇒人間関係、利害関係者との関係、従業員の扱い方
・自分の思い(見方)が相手を活かす(成長させる)
・人は学んで、決意し、実行するプロセスを繰り返し、成長の螺旋を作ることができる
・刃を研ぐの応用
①生活様式に見合った自分の健康状態を維持する活動で、長期にわたって継続できるものをリストアップしてみる。
②リストアップした活動のうちひとつを選び、今週の目標を入れる。1週間が終わったところで自己評価を行う。目標が達成されていなければ、自分の価値観で判断して考える。
③同じように精神的側面の活動リストを作る。それから今改善したい人間関係をリストアップする。あるいは公的成功を必要とする場面を明確にする。そこから項目をひとつ選び目標に取り入れ実行し評価する。
④毎週4つの側面において刃を研ぐ活動を実行し結果を評価することを決意する
○インサイド・アウト
子供に相続できるもので永遠の価値を持つものはルーツと翼である
子供に翼を与えるということは悪い脚本を乗り越える(流れを変える)力を与えること
………………………………………………………
砂川よしひろ(沖縄県浦添市在)
教育アドバイサー 子育て・学習支援
企画編集者(自分史 地域史 社史の制作)
コピーライティング 人生コーチング
090-4981-8723 sunayoshi222@softbank.ne.jp
………………………………………………………
・パラダイム(世界を見る見方、地図、レンズ)認識、理解、解釈を決めるもの
今までの経験がパラダイムを決めている
世界をあるがままに見ているのではなく、自分たちがあるがままに見ている
見方が変われば、あり方が変わる
レンズや地図は主観的事実、客観的事実は原則からなる
・パラダイム転換(あるひとつのものの見方が別の見方へ移行すること)
・原則は深い基礎的な真理
・インサイド・アウト(内から外へ)、自分自身の内面(インサイド)
・習慣の要素
個性主義 (テクニック) 上辺だけの問題に対応 表面的な成功 二次的なもの
人格主義 (根本な土台) 人格に深く内面な対応 真の成功 一次的なもの
知識(何をするか、なぜするか)
スキル(どうやってするか)
やる気(実行したい気持ち)
●第一部 私的成功
○第1の習慣
主体性を発揮する
・多くの人は社会の鏡(社会の通念、人々の考え)からパラダイムや考えを得ている
・人間は刺激と反応の間に選択の自由がある
自分の反応を選択する能力
主体性をもつ=自分の人生に責任をとる
反応的 周りの物的な環境に大きく影響を受ける
主体的 自分の価値観に基づき率先力を持って行動
・自分の身に何かが起こるのではなく、それにどう反応するかが重要
率先力 自分から進んで状況を改善する行動を起こすこと
関心の輪 関心を持っている事柄
影響の輪 関心を持っている事柄であり
直接コントロールできるもの
・直面する3種類の問題
直接的にコントロールできる問題(自分の行動と関係している問題)
間接的にコントロールあるいは影響できる問題(他人の行動と関係している問題)
全くコントロールできない問題(誰も影響できない問題、過去の出来事)
・問題は自分の外にあると考えることが問題である(他人のせいにしない)
・結果は選択できないため、間違いは修正しなくてはならない
・目標を設定し行動、自分自身に約束をして守る
・主体性を発揮するの応用
①自分自身と周りの人々の反応的な言葉を2日間聞いてみる
②近い将来、直面するであろう状況、反応的になることを過去の経験からひとつ選んで影響の輪を考慮して主体的な反応を示すためにでき
ることを考えてみる。そして、主体的に反応している自分の姿、行動をイメージして刺激と反応の間のを思い起こし、選択の自由を活用す
る約束を自分自身にする
③仕事や私生活で抱えている問題をひとつ選択する。それが直接的か間接的かあるいは全くコントロールできない問題にあたるか考える。
その問題を解決するために自分の影響の輪の中でとれる具体的な行動を打ち出して実行する
④主体性の30日間のテスト(目標を設定し行動、自分自身に約束をして守る)を実行する。影響の輪の変化を意識してみる。
○第2の習慣
目的を持って始める
・目的を持って始めるということはすべての行動を測るための尺度として人生最後の姿(自分の葬式、友人や家族、知人になんて言ってもら
いたいか)を描き、それを念頭において今日という1日を始めること
・目的を持って始めるということは人生のはしごの掛け違いをなくす
・すべてのものは2度つくられる
知的な第1の創造 設計図、計画、脚本 第2の習慣
物的な第2の創造 物の組み立て、実行 第3の習慣
・第2の習慣は自己リーダーシップの原則に基づいている
リーダーシップとは正しい方向に導くこと、マネジメントは物事を正しく行うこと
・ミッション・ステートメント(個人的な憲法、信条)
自分はどうなりたいのか、何をしたいのか、自分の行動の基礎となる価値観、原則明らかにする
・原則中心の生活をすることで安定性、方向性、知恵ならびに力が発揮される
・視野を広げてイメージ化、自己宣言を書く
・自己宣言は個人的、積極的、現在進行形、イメージ化できる、感情を表すの5つの要素
(例)子供たちが悪いことをするとき、私(個)は知恵・愛ある態度(積)で対応する(現)ことに深い満足感(感情)を覚える(イ)
・役割(生活上の各領域)と目標
・目的を持って始めるの応用
①葬式のイメージ化をして、家族、友人、仕事、社会、地域などの人格、貢献、達成したことなどを経験して思いを記録する
②自分の生活における役割を書いてバランスに満足しているか考える
③個人的なミッション・ステートメントを書き始める時間をスケジュールにいれる
④自分の今の中心においているものを考えて生活のパターンが望ましいものか考える
⑤個人的なミッション・ステートメントを作成するのに役立つアイデアや引用文を集める
⑥近い将来直面するプロジェクトのひとつを取り上げて知的創造の原則を活用してみる。望んでいる結果とそれを作り出すのに必要な行動
・手順を書いてみる
⑦原則を家族や職場の人と分かち合い、家族や職場のミッション・ステートメントを作るプロセスを開始する。
○第3の習慣
重要事項を優先する
・活動を定義するのは緊急度と重要度であり時間管理のマトリックスで表現できる
・第二領域に集中することで自己管理
・第三領域、第四領域にノーといえる大きなイエスが大切
第一領域 緊急で重要
第二領域 緊急でないが重要
第三領域 緊急で重要でない
第四領域 緊急でなく重要でない
・新しい時間管理(第二領域時間管理)ツールの6つの大切な特徴
①一貫性 自分のビジョン・ミッション、役割と目標、優先順位と計画を調和させられミッション・ステートメントを入れる場所が必要。
そして役割、目標を管理する場所も重要
②バランス 健康、家族、仕事、準備、自己啓発など大切な事柄が日々の生活で疎かにならないよう生活のぞれぞれの役割を管理できるよ
うになっていること
③第二領域の集中 週単位の計画で優先順位をスケジュールに入れる
④人間重視 大切な人間関係について考えてあるもの
⑤柔軟性 自分のスタイルやニーズにあうもの、やり方に柔軟に合わせられるもの
⑥携帯性 携帯するのに便利なもの
・第二領域に集中した計画の4つの基本的なステップ
①役割を定義する 生活の主な役割を考える
(例)夫、父親、商品開発者、研究員、部下を育てる者、友人、人生を楽しむ者、健康維持
②目標設定 次の1週間で各役割において達成したい目標を2~3つ設定する
(例)妻とコンサート、マーケット調査、夏期休暇の旅行計画
③スケジュール化 目標を念頭において特定の時間を割り当てる。 時間の余裕も残す
④日々の対応 日々の出来事によってスケジュールを変更させる。 優先順位をつける
長期的な計画 ミッション・ステートメント→役割→目標
1週間の計画 役割→目標→計画→実行、デレゲーション
・デレゲーション
デレゲーション 他の人に仕事を任せること
使い走りのデレゲーション(指示しないとできない)
完全なデレゲーション(指示なし、結果に焦点を合わせる、結果に責任を持たせる)
・完全なデレゲーション行うために
望む結果 出すべき結果に明確な相互理解を得る
ガイドライン 結果を出すにあたりルールがあれば明確に、少ない方がいい
使える資源 望む結果を出すために活用できる人的、金銭的、技術的、組織的な範囲
責任に対する報告 結果を評価する基準、評価する人、報告と評価、期限を具体的に
履行(不履行)の結果 評価の結果はどうなるか(賞罰)、金銭的な報酬など
・重要事項を優先するの応用
①自分の私生活、職場においてこれまで疎かにしていた第二領域の活動をひとつ打ち出す
②時間管理のマトリックスを書いて、それぞれの領域にどれぐらい時間を使っているか考える。それから3日間にわたり15分間隔で実際の時
間の使い方を記録する
③人に任せられそうなことをピックアップしてみる。そして任せる相手も書いてみる。デレゲーション、訓練のプロセスを開始するにはど
うすればいいか考える
④来週の計画を立てる。まず、その週の役割と目標を書き、具体的な行動計画に移す。1週間の終わりに計画が目標や価値観に反映されてい
たか評価する
⑤毎週、週単位の計画を立てる決意し、その計画を立てる時間をスケジュールに入れる
⑥自分の使っているツールを新しい時間管理ツールに切り替える。
●第ニ部 公的成功
信頼残高 ある関係において築かれた信頼のレベルを表すもの
礼儀正しい行動、親切、正直、約束で残高が貯まり、残高不足だと信頼関係が崩れていく
・信頼残高を作る6つの大切な預け入れ
①相手を理解する
相手にとって大切なことを、自分にとっても大切なことに思う必要がある
②小さいことを大切にする
小さな心遣いと礼儀は大切で、小さな無礼と不親切、無神経は大きな引き出しとなる
③約束を守る
約束を守ることは大きな預け入れであり、破ることは大きな引き出しである
④期待を明確にする
人間関係の問題は役割と目標を取り巻くあいまいな期待、お互いの期待像の相違
⑤誠実さを示す
個人的な堅実さが信頼を築き、様々な預け入れの基礎となる
誠実さを示す重要な方法のひとつは、その場にいない人に対して忠実になること
すべての人に対して平等に同じ原則に沿って接する
⑥引き出しをしてしまったときは誠意をもって謝る
間違いを犯すことはひとつの問題だがそれを認めないのはもっと大きな問題
愛の基礎的な法則 見返りを求めない無条件の愛
人生の基礎的な法則 協力、貢献、自制、誠実に沿って生活する
・Pの問題はPCの機会である
第4の習慣
Win-Winを考える
・人間関係の6つのパラダイム
①Win-Win
自分も勝ち、相手も勝つ。それぞれの当事者が欲しい結果を得ること
②Win-Lose
自分が勝ち、相手が負ける
③Lose-Win
自分が負けて、相手が勝つ
④Lose-Lose
自分も負けて、相手も負ける
⑤Win
自分だけの勝ちを考える
⑥Win-WinまたはNo Deal
Win-Winの合意または取引条件に至らなければ取引しないことに合意する
・Win-Winを支える5つの柱
①人格
・誠実、廉潔 自分自身に置く価値
・成熟 勇気と思いやりのバランス
勇気=自分の気持ちや信念を表現する、思いやり=相手の気持ちや信念を尊重する
・豊かさマインド すべての人を満足させることが可能であるというパラダイム
欠乏マインド 人生をゼロサムゲームとしてみている
②関係
・人格という土台上に立てられ維持されるもの、信頼残高こそがWin-Winの本質
③合意
・Win-Winの実行協定 5つの要素
望む結果 手段ではなく、何をいつまでに達成するか明確にする
ガイドライン 望む結果を達成するにあたり守るルール(原則、方針)を明確にする
使える資源 望む結果を達成ために活用できる人的、金銭的、技術的、組織的な範囲
責任に対する報告 評価基準、評価者および評価の時期を設定する
履行(不履行)の結果 プラス、マイナス自然・必然的な結果を設定、賞罰などを明確に
金銭的な報酬 給与、株、小遣い、罰金
心理的な報酬 評価、称賛、感謝、尊敬、信頼
与える範囲 研修、職場内訓練
与える責任の範囲 その人の権限の及ぶ範囲
④システム
・研修、計画立案、コミュニケーション、情報伝達、予算、報酬システムなど
⑤プロセス
・4つのステップ
1.問題を相手の立場から見る、相手を理解し、相手のニーズや心配や関心事を表現する
2.対処しなければならない課題や関心事(立場でない)を明確にする
3.完全に納得できる解決には、どういう結果を確保しないといけないか明確にする
4.その結果を達成するための新しい案や選択肢を打ち出す
・Win-Winを考えるの応用
①これから誰かと一緒に、合意にいたらなければならない状況、解決に向けて交渉しなければならい状況をひとつ選ぶ。その状況において勇気と思いやりのバランスを維持することを決意する
②自分の生活の中でWin-Winのパラダイムを妨げている要因や障害をリストアップする。この障害を取り除くために自分の影響の輪の中でなにができるだろうか考える。
③具体的にWin-Winの合意をつくりたい相手をひとり選ぶ。相手の立場に立って、相手の望んでいる結果を書いてみる。次に自分の観点から自分の望んでいるWinを確保するためにはどういう結果が必要なのか書いてみる。相手と話して、双方が満足する解決策を見つけるまでコミュニケーションを続ける用意があるか聞いてみる。
④自分の生活の中で重要な人間関係を3つ選ぶ。今の信頼残高はどれくらいあるだろうか、
その残高を増やすにはどんな預け入れができるかを書いてみる
⑤自分の今まで脚本づけ(Win-Loseなど)を考えてみる。その脚本づけが他の人と接し方にどういう影響を与えているか、その脚本のもととなっているのは何なのか、その脚本からつくられたパラダイムが自分が直面している現実に十分に対応できるものか検討する。
⑥難しい状況においても、相互利益を求める模範的な人を考えてみる。どうしたらこの人の模範をもっと身近に観察し、それから学べるかを考えてみる。
第5の習慣
理解してから理解される
・まず相手を理解するように努め、その後で自分を理解してもらう
・人生の最も大切なスキルはコミュニケーション(読む、書く、話す、聞く)
・4つのレベルで聞いている
①無視をする あるいは実際に聞いていない
②聞いたふりをする あいづちを打つという具合
③選択的に聞く 会話の部分部分しか耳に入れようとしない
④注意して聞く 注意深く集中して相手の言葉を聞くようになる
これよりも上の最も高い傾聴のレベルは感情移入の傾聴法
スキル中心な傾聴は基本的に自叙伝的な聞き方になっている
感情移入をして聞くことは相手の立場、見地から見ることで大きな預け入れになる
まず理解することが人生のあらゆる場面に作用する正しい原則
・4つの自叙伝的な反応と感情移入
①評価する 賛成、もしくは反対する
②探る 自分の視点から質問する
③助言する 自分の経験に基づき、助言やアドバイスを与える
④解釈する 自分の動機や行動をもとに相手の動機や行動を捉え、解釈、説明する
本当に理解したい気持ち、人格、相手との信頼残高、感情移入のスキルを身につけるまでは他の人の見地に立って、その人の見ている世界を見ることは絶対にできない
・感情移入の傾聴の4つの段階
①話の中身を繰り返す
(例)父さん、学校なんてもういやだよ⇒学校がいやなんだね
②話の中身を自分の言葉に置き換える
(例)父さん、学校なんてもういやだよ⇒そうか、学校に行きたくないんだ
③感情を反映する
(例)父さん、学校なんてもういやだよ⇒なんだかイライラしてるようだね
④話の中身を自分の言葉に置き換え、同時に感情を反映する(②+③)
(例)父さん、学校なんてもういやだよ⇒学校に行きたくなくて、なんだかイライラしてるようだね
・効果的に質問したり、助言を与えられる機会があったとしても、反応が感情的になるときには感情移入の傾聴に戻らなくてはならない
・たいていの場合は、人は外からの助言など必要ない。相手は本当に心の中を打ち明けることができれば、自分の問題を自分なりに整理し、その過程で解決策も明確になる
・一方で他の人の助言や協力が必要な場合がある。相手の利益を考え、感情移入の傾聴をし、相手の立場で問題を理解し、その解決策を一緒に探すこと
・エトス・パトス・ロゴス
エトス (人格) 個人の信頼性、信頼残高
パトス (人間関係) 感情移入、相手の感情的側面を理解する
ロゴス (理論展開) 理論、プレゼンテーションの論理展開
・手の目を通して人生を見つめることで、インサイド・アウトのアプローチにより影響の輪が広がり、関心の輪にあった様々な事柄に影響を及ぼす力ができる
・自叙伝を一度棚上げして、誠意をもって相手を理解する努力をしてみる
・理解してから理解されるの応用
①信頼残高が赤字になっている関係をひとつ考えてみる。相手の見地からその問題を理解しようとし、それを書き留める。次にその人と接するとき、理解を求めて聴くようにし、書き留めたことと聴いたことを比較する。自分の思い込んでたことと相手の立場や気持ちをどれぐらい理解していたか考える
②身近な人に感情移入、他人の話を真剣に聴くことを練習したい胸を伝え、1週間後にフィールドバックを求める。結果や気持ちを知る。
③他人のコミュニケーションを観察する機会があったら、耳をふさいで、目で見てみる。
言葉だけではわからない感情を読み取ってみる
④次回、不適切な自叙伝(探り、評価、助言、解釈)を挟んでいると気がついたら、その状況を預け入れに取り換えるために、それを認めて謝るようにする。「ごめんなさい。本当に理解しようとしていたのではないことに、今自分で気がつきました。もう一度最初から初めてもいいでしょうか」というように
⑤次にプレゼンテーションをするときに、それに感情移入に基づき行ってみる。相手の立場を相手以上に上手く説明してみる。それから自分の立場を相手の見地から説明し理解してもらう。
○第6の習慣
相乗効果を発揮する
・創造的な協力の原則
・相乗効果とは全体の合計が各部分の和より大きくなること
・第三案を探し、双方が満足する案を話し合いで導き出す
・違う意見を得ることこそが人間関係のもたらす利点
・相乗効果の本質は相違点、つまりは知的、情緒的、心理的な相違点を尊ぶこと
・すべての人は自分のあるがままに世界を見ていることを理解すること
・自分の物の見方に限界を認め、他の人のパラダイムと考え方に接する
・Win-Winの関係は信頼と協力が高い相乗効果的コミュニケーションがとれる
場の分析 駆動力と抑止力の均衡
現在得られている結果は均衡にある
駆動力 上向きの成長を促す
正の、合理的、論理的、意識的、経済的
抑止力 下向きの妨げを促す
負の、感情的、非論理的、無意識、社会的
・相乗効果を発揮するの応用
①自分と違った意見を頻繁に述べる人を考える。その相違点を、第三案を打ち出すたえの踏み台にする方法を考える。今自分が直面している問題やプロジェクトについて、その人の意見を求めるよにする。そして意見に価値を置き、それを真剣に受け止める。
②気に障る人をリストアップする。自分がより高いレベルの内面的安定を持ち、その相違点を尊ぶようにすることによって、彼らの持つ観点が相乗効果を生み出す原動力にならないか考える
③高いチームワークと相乗効果が欲しい状況を考えてみる。必要な相乗効果を支えるためには、どういう条件を整える必要があるか考える。また、そのために自分がなにができるのか考える
④今後、意見の相違やぶつかり合いが生じたとき、その人の立場を裏づける考えを理解しようとする。その人の意識している事柄を考慮に入れて、その問題を創造的かつ双方の利益になるような方法で解決していく。
●第三部 再新再生
○第7の習慣
刃を研ぐ
・バランスのとれた自己再新再生の原則
・肉体、精神、知性は毎日の私的成功
・再新再生の4つの側面
①肉体的側面(自制と責任感が強められる、第1の習慣)
・バランスのとれた栄養のある食事、十分な休養、定期的な運動
・運動 1週間のうち3~6時間、1日30分くらい目安
持久力 有酸素運動、心臓の能力向上(ジョギング、水泳など)
柔軟性 ストレッチング(有酸素運動の前後にウォーミングアップ、クールダウン)
強さ 筋肉に負かをかける運動(多少とりいれればいい筋肉トレーニング)
②精神的側面(自己リーダーシップが育成される、第2の習慣)
リラックスして精神を落ち着かせる、見つめ直す(祈り、瞑想など)
③知的側面(自己マネジメントを支えるもの、第3の習慣)
テレビは目的をもって見る、本を読む、文章を書くなど
④社会、情緒的側面(真の理解を深め、人の成功を喜ぶ、第4~6の習慣)
人の役に立つ貢献(ボランティア)
・組織の場合
①肉体的側面 ⇒経済的側面
②精神的側面 ⇒組織の目的、貢献の意味の発見
③知的側面 ⇒人の才能の開発、活用、評価
④社会、情緒的側面 ⇒人間関係、利害関係者との関係、従業員の扱い方
・自分の思い(見方)が相手を活かす(成長させる)
・人は学んで、決意し、実行するプロセスを繰り返し、成長の螺旋を作ることができる
・刃を研ぐの応用
①生活様式に見合った自分の健康状態を維持する活動で、長期にわたって継続できるものをリストアップしてみる。
②リストアップした活動のうちひとつを選び、今週の目標を入れる。1週間が終わったところで自己評価を行う。目標が達成されていなければ、自分の価値観で判断して考える。
③同じように精神的側面の活動リストを作る。それから今改善したい人間関係をリストアップする。あるいは公的成功を必要とする場面を明確にする。そこから項目をひとつ選び目標に取り入れ実行し評価する。
④毎週4つの側面において刃を研ぐ活動を実行し結果を評価することを決意する
○インサイド・アウト
子供に相続できるもので永遠の価値を持つものはルーツと翼である
子供に翼を与えるということは悪い脚本を乗り越える(流れを変える)力を与えること
………………………………………………………
砂川よしひろ(沖縄県浦添市在)
教育アドバイサー 子育て・学習支援
企画編集者(自分史 地域史 社史の制作)
コピーライティング 人生コーチング
090-4981-8723 sunayoshi222@softbank.ne.jp
………………………………………………………
2016年04月07日
自分を変える
「自分を変える方法」~白坂氏のFBより
人が変わる途中過程というのは、みんな同じ。
(1)3日間で環境を変える
(2)3週間毎日やることで無意識の習慣化が始まる
(3)3か月後に変われている
一番分かりやすいのは、身体の変化です。
一番分かりにくいのは、心の変化です。
身体の変化は科学的に分かって来ます。
毎日・毎日消滅と生成を繰り返し続けている細胞は、
3か月後では全て新しいものに変わっています。
だから、生物学的には3か月前の自分と今の自分は別人です。
でも、そうは言われても変わっている感じがしないのは、
記憶が連続しているから。
「私とはこういう人間だ」と思い込んでいれば、
どれだけ身体の細胞が変わっても、人としての本質は何も変われません。
しかし、過去の記憶を潔く捨て去り、新しい考え方を取り入れようと、
3か月間毎日取り組み続けたならば、必ず、心の方も変われます。
心の方が変われたか・どうかは、
自分の感じ方が変わったかどうかで分かります。
全く同じ対象に対して、以前と今で感じ方が変わっていたとしたら、
その人は身体だけではなく、心も変わっています。
たとえば、
・以前はテレビを観るのが大好きだったのに、
今はテレビに嫌悪感を感じる、とか
・以前はタバコを吸うのが大好きだったのに、
今はタバコの臭いに嫌悪感を感じる、とか
・以前は暇つぶしが大好きだったのに、
今は暇つぶしに嫌悪感を感じる、とか、、、
全く同じ対象にも関わらず、
そのものに対しての感じ方が変わっていたとしたら、
その人は、心も変わっています。
当然、目標達成もしやすくなります。
以前は食べるのが大好きだった人が、
食べることに嫌悪感を感じ始めたら
痩せられるのは当たり前。別にダイエットに限らず、
全ての目標達成が同じです。
目標達成を阻害するものに嫌悪感を感じ、
目標達成を支援する行動に好意を感じられたら、
目標を達成する方が当たり前
この感じ方が変わるのに最小の期間が3か月です。
それより短いと何も変わりません。記憶に引きずられ、
過去の自分へと引きずり戻されます。
逆に、
3か月間自己改革に本気で取り組み続ければ変われます。
ただし、だからと言って「3か月間、本気で取り組むぞ!!」
と叫んでも、ほぼ無駄です。
なぜなら、気合いで変えようとしているから。
気合いで何とかなるのは、3か月間ではなく、
たった2日間。
どんなに頑張っても、わずか3日間が限界。
途中の3週間でさえ無理です。
だから、
やる気がある最初の2日間のうちに、勢いで環境の方を変えてしまう
3か月間やるしかない環境を先に作ってしまう。
自分を追い込む。こどもたちの塾と全く同じです。
家では勉強は出来ない。
塾だと勉強するしかない環境だから、勉強をする。
(1)3日間で環境を変える
(2)3週間毎日やることで無意識の習慣化が始まる
(3)3か月後に変われている
自分がやる気になれたと思ったら、
その勢いで3日以内に環境を先に変えてしまう。
やるしかない環境を準備する。自分を追い込む。
そして、やるしかない環境で3週間毎日やって、
目標達成に必要な行動を無意識の習慣でもやれるようにしていく。
そして、その後さらに3か月間は続ける。
そうすると、身体はもちろん、心も変わっています。
以前は大好きだった何かに嫌悪感を感じ、
逆に、以前はやりたくないと思っていたことを
楽しくやれるようになっています。
つまり、
人は、3か月間本気で取り組めば、心身ともに変われる
砂川よしひろ(沖縄県浦添市在)
教育アドバイサー 子育て・学習支援
企画編集者(自分史 地域史 社史の制作)
コピーライティング 人生コーチング
090-4981-8723 sunayoshi222@softbank.ne.jp
人が変わる途中過程というのは、みんな同じ。
(1)3日間で環境を変える
(2)3週間毎日やることで無意識の習慣化が始まる
(3)3か月後に変われている
一番分かりやすいのは、身体の変化です。
一番分かりにくいのは、心の変化です。
身体の変化は科学的に分かって来ます。
毎日・毎日消滅と生成を繰り返し続けている細胞は、
3か月後では全て新しいものに変わっています。
だから、生物学的には3か月前の自分と今の自分は別人です。
でも、そうは言われても変わっている感じがしないのは、
記憶が連続しているから。
「私とはこういう人間だ」と思い込んでいれば、
どれだけ身体の細胞が変わっても、人としての本質は何も変われません。
しかし、過去の記憶を潔く捨て去り、新しい考え方を取り入れようと、
3か月間毎日取り組み続けたならば、必ず、心の方も変われます。
心の方が変われたか・どうかは、
自分の感じ方が変わったかどうかで分かります。
全く同じ対象に対して、以前と今で感じ方が変わっていたとしたら、
その人は身体だけではなく、心も変わっています。
たとえば、
・以前はテレビを観るのが大好きだったのに、
今はテレビに嫌悪感を感じる、とか
・以前はタバコを吸うのが大好きだったのに、
今はタバコの臭いに嫌悪感を感じる、とか
・以前は暇つぶしが大好きだったのに、
今は暇つぶしに嫌悪感を感じる、とか、、、
全く同じ対象にも関わらず、
そのものに対しての感じ方が変わっていたとしたら、
その人は、心も変わっています。
当然、目標達成もしやすくなります。
以前は食べるのが大好きだった人が、
食べることに嫌悪感を感じ始めたら
痩せられるのは当たり前。別にダイエットに限らず、
全ての目標達成が同じです。
目標達成を阻害するものに嫌悪感を感じ、
目標達成を支援する行動に好意を感じられたら、
目標を達成する方が当たり前
この感じ方が変わるのに最小の期間が3か月です。
それより短いと何も変わりません。記憶に引きずられ、
過去の自分へと引きずり戻されます。
逆に、
3か月間自己改革に本気で取り組み続ければ変われます。
ただし、だからと言って「3か月間、本気で取り組むぞ!!」
と叫んでも、ほぼ無駄です。
なぜなら、気合いで変えようとしているから。
気合いで何とかなるのは、3か月間ではなく、
たった2日間。
どんなに頑張っても、わずか3日間が限界。
途中の3週間でさえ無理です。
だから、
やる気がある最初の2日間のうちに、勢いで環境の方を変えてしまう
3か月間やるしかない環境を先に作ってしまう。
自分を追い込む。こどもたちの塾と全く同じです。
家では勉強は出来ない。
塾だと勉強するしかない環境だから、勉強をする。
(1)3日間で環境を変える
(2)3週間毎日やることで無意識の習慣化が始まる
(3)3か月後に変われている
自分がやる気になれたと思ったら、
その勢いで3日以内に環境を先に変えてしまう。
やるしかない環境を準備する。自分を追い込む。
そして、やるしかない環境で3週間毎日やって、
目標達成に必要な行動を無意識の習慣でもやれるようにしていく。
そして、その後さらに3か月間は続ける。
そうすると、身体はもちろん、心も変わっています。
以前は大好きだった何かに嫌悪感を感じ、
逆に、以前はやりたくないと思っていたことを
楽しくやれるようになっています。
つまり、
人は、3か月間本気で取り組めば、心身ともに変われる
砂川よしひろ(沖縄県浦添市在)
教育アドバイサー 子育て・学習支援
企画編集者(自分史 地域史 社史の制作)
コピーライティング 人生コーチング
090-4981-8723 sunayoshi222@softbank.ne.jp
2016年04月01日
アドラー心理学・教育に関する48の名言
受験シーズが終わって、中学校教師をしている息子が読んでいたアドラー心理学の本が気になった。彼から数冊借りて読ませてもらった。これは心理学だけではなく哲学書、そして教育に必要なエッセンスが凝縮された実践書であると思いました。
新年度を迎えるにあたって、日ごろ当ブログを読んでいただいている皆様に「アドラー心理学・教育に関する48の名言」(砂川よしひろ編著)をお贈りします。アドラーの考え方・趣旨は変えぬよう留意しながらコンパクトに読みやすくさせていただきました。48項目のすべてが正しいとは言いませんが、皆様にとって何か思いあたること、子育ての参考になることがすこしでもあれば幸いです。
アルフレッド・アドラー(1870年2月7日~1937年5月28日)は、オーストリア出身の精神科医、心理学者、社会理論家。ジークムント・フロイトおよびカール・グスタフ・ユングと並んで現代のパーソナリティ理論や心理療法を確立した1人
アドラー心理学・
教育に関する48の名言 20160401
1.世話好きな人は、単に優しい人なのではない。相手を自分に依存させ、自分が重要な人であることを実感したいのだ。
2.悲しいから涙を流すのではない。相手を責め、同情や注目を引くために泣いているのだ。
3.カッときて自分を見失い怒鳴ったのではない。相手を支配するために、怒りという感情を創り出し利用したのだ。
4.子供は感情でしか大人を支配できない。大人になってからも感情を使って人を動かそうとするのは、幼稚である。
5.人はライフスタイル(=性格)を10歳くらいまでに自分で決めて完成させる。そして、それを一生使い続けるのだ。
6.子供にとって家族は「世界そのもの」であり、親から愛されなければ生きていけない。そのための命がけの戦略が、そのまま性格の形成につながるのだ。
7.叱られたり、ほめられたりして育った人は、叱られたり、ほめられたりしないと行動しなくなる。そして、評価してくれない相手を、敵だと思うようになるのだ。
8.「よくできたね」とほめるのではない。「ありがとう、助かったよ」と感謝を伝えるのだ。感謝される喜びを体験すれば、自ら進んで貢献を繰り返すだろう。
9.行動に問題があるとしても、その背後にある動機や目的は、必ずや「善」である。
10.すべての悩みは対人関係の課題である。仙人のような世捨て人でさえも、実は他人の目を気にしているのだ。
11.それが「あなたの課題」ならば、たとえ親に反対されても従う必要はない。自分の課題に足を踏み込ませてはいけないのだ。
12.「暗い」のではなく「優しい」のだ。「のろま」ではなく「ていねい」なのだ。「失敗ばかり」ではなく「たくさんのチャレンジをしている」のだ。
13.ほめてはいけない。ほめることは「あなたは私よりも下の存在だ」「どうせあなたにはできっこない」と相手に伝えることに等しいからだ
14.「信用」するのではなく「信頼」するのだ。「信頼」とは裏付けも担保もなく相手を信じること。裏切られる可能性があっても相手を信じるのである。
15.苦しみから抜け出す方法はたった一つ。他の人を喜ばせることだ。「自分に何ができるか」を考え、それを実行すればよい。
16.「この子は言葉を覚えるのが遅いので・・・・・・」と母親が子どもの通訳を買って出る。すると子どもは、自分で話す必要がなくなり、本当に言葉が遅くなるだろう。
17.罰を与えるのではない。結末を体験させるのだ。子どもが食事の時間になっても帰ってこなければ、一切叱らずに食事を出さなければよい。
18.問題行動に注目すると人はその問題行動を繰り返す。叱ることは、悪い習慣を身につけさせる最高のトレーニングなのだ。
19.叱られたり、ほめられたりして育った人は、叱られたりほめられたりしないと行動をしなくなる。そして、評価してくれない相手を敵だと思うようになるのだ。
20.すべての悩みは対人関係の課題である。仙人のような世捨て人でさえも、実は他人の目を気にしているのだ。
21.相手を「支配」するために「怒り」という感情を創り出し利用したのだ。怒りは無意識の感情ではない。認識して利用するのだ。
22.「よくできたね」とほめるのではない。「ありがとう、助かったよ」と感謝を伝えるのだ。
23.大切なことは「共感」することだ。
「大切なのは共感することだ。共感とは、相手の目で見、相手の耳で聞き、相手の心で感じることである」
24.人間は自分の人生を描く画家である。 あなたを作ったのはあなた。 これからの人生を決めるのもあなた。
25.健全な人は、相手を変えようとせず自分がかわる。不健全な人は、相手を操作し、変えようとする。
26.「やる気がなくなった」のではない。 「やる気をなくす」という決断を自分でしただけだ。
27.あなたが出来ない理由は、環境を言い訳にして「努力から逃げている」から。
28.人はあらゆる手を使って自分を重要人物だと思わせたい(世話を焼くことも、リストカットも)
29.人は「注目を集めたい」だめなら「力を示す」だめなら「復讐する」だめなら「回避する」
30.感情は「相手を操作・支配するため」と「自分自身を突き動かすため」に利用される。
31.「感情に支配される」のではなく、「背中押し」又は「ブレーキ」のために感情を利用すること。
32.自分でやると失敗するかもしれないから誰かにやってほしい、と思う人は社会的に孤立する。
33.「相手」は誰で、「目的」は何か?を推測しながら相手を観察する。
34.「理性と感情」「意識と無意識」は対立しない。同じ目標に向かって補い合っている。
35.子供は親の愛や関心を引くために戦略を実行している。それが性格となる。
36.0歳から10歳までの家族の、関係図、人間関係、雰囲気、共有された価値、がその人の性格を形作る。
37.相手の問題行動を直すには、共に信頼関係を築いてしばらく経ってから自分がどう考えるかを伝えること。
38.問題行動を叱ると、注目することになる。だから相手はやめない。だから正しい行動のみに注目する。
39.強制を辞める。相手に自分で決めさせる。自分を信じ他人を信じ居場所を見つける。
40.他人の評価を気にする人は自分のことばかり考えている人。つまり勇気がない人。
41.誰からもほめられず認められなくても自分が相手に貢献できていることそのものに満足すること。
42.出来ている部分に着目して感謝する。
43.共感とは「相手の置かれている状況や考え方、意図、感情、関心などに関心をもつこと」
44.「怒り」は「さみしさ」「悔しさ」「悲しさ」が先にあり、それが相手に理解してもらえないときに「怒る」
45.原因究明はせず、分析もせず、いきなり「こんなやり方はどうかな?」と提案する。
46.あらゆる人間関係のトラブル原因は他人の課題に土足で踏み込む、から。
47.自分の課題とは「その問題を放置した場合、不利益を被るのは誰か?」で考える。
48.自分と他者との「課題の分離」が出来るようになるとシアワセの第一歩である。
砂川よしひろ(沖縄県浦添市在)
教育アドバイサー 子育て・学習支援
企画編集者(自分史 地域史 社史の制作)
コピーライティング 人生コーチング
090-4981-8723 sunayoshi222@softbank.ne.jp
新年度を迎えるにあたって、日ごろ当ブログを読んでいただいている皆様に「アドラー心理学・教育に関する48の名言」(砂川よしひろ編著)をお贈りします。アドラーの考え方・趣旨は変えぬよう留意しながらコンパクトに読みやすくさせていただきました。48項目のすべてが正しいとは言いませんが、皆様にとって何か思いあたること、子育ての参考になることがすこしでもあれば幸いです。
アルフレッド・アドラー(1870年2月7日~1937年5月28日)は、オーストリア出身の精神科医、心理学者、社会理論家。ジークムント・フロイトおよびカール・グスタフ・ユングと並んで現代のパーソナリティ理論や心理療法を確立した1人
アドラー心理学・
教育に関する48の名言 20160401
1.世話好きな人は、単に優しい人なのではない。相手を自分に依存させ、自分が重要な人であることを実感したいのだ。
2.悲しいから涙を流すのではない。相手を責め、同情や注目を引くために泣いているのだ。
3.カッときて自分を見失い怒鳴ったのではない。相手を支配するために、怒りという感情を創り出し利用したのだ。
4.子供は感情でしか大人を支配できない。大人になってからも感情を使って人を動かそうとするのは、幼稚である。
5.人はライフスタイル(=性格)を10歳くらいまでに自分で決めて完成させる。そして、それを一生使い続けるのだ。
6.子供にとって家族は「世界そのもの」であり、親から愛されなければ生きていけない。そのための命がけの戦略が、そのまま性格の形成につながるのだ。
7.叱られたり、ほめられたりして育った人は、叱られたり、ほめられたりしないと行動しなくなる。そして、評価してくれない相手を、敵だと思うようになるのだ。
8.「よくできたね」とほめるのではない。「ありがとう、助かったよ」と感謝を伝えるのだ。感謝される喜びを体験すれば、自ら進んで貢献を繰り返すだろう。
9.行動に問題があるとしても、その背後にある動機や目的は、必ずや「善」である。
10.すべての悩みは対人関係の課題である。仙人のような世捨て人でさえも、実は他人の目を気にしているのだ。
11.それが「あなたの課題」ならば、たとえ親に反対されても従う必要はない。自分の課題に足を踏み込ませてはいけないのだ。
12.「暗い」のではなく「優しい」のだ。「のろま」ではなく「ていねい」なのだ。「失敗ばかり」ではなく「たくさんのチャレンジをしている」のだ。
13.ほめてはいけない。ほめることは「あなたは私よりも下の存在だ」「どうせあなたにはできっこない」と相手に伝えることに等しいからだ
14.「信用」するのではなく「信頼」するのだ。「信頼」とは裏付けも担保もなく相手を信じること。裏切られる可能性があっても相手を信じるのである。
15.苦しみから抜け出す方法はたった一つ。他の人を喜ばせることだ。「自分に何ができるか」を考え、それを実行すればよい。
16.「この子は言葉を覚えるのが遅いので・・・・・・」と母親が子どもの通訳を買って出る。すると子どもは、自分で話す必要がなくなり、本当に言葉が遅くなるだろう。
17.罰を与えるのではない。結末を体験させるのだ。子どもが食事の時間になっても帰ってこなければ、一切叱らずに食事を出さなければよい。
18.問題行動に注目すると人はその問題行動を繰り返す。叱ることは、悪い習慣を身につけさせる最高のトレーニングなのだ。
19.叱られたり、ほめられたりして育った人は、叱られたりほめられたりしないと行動をしなくなる。そして、評価してくれない相手を敵だと思うようになるのだ。
20.すべての悩みは対人関係の課題である。仙人のような世捨て人でさえも、実は他人の目を気にしているのだ。
21.相手を「支配」するために「怒り」という感情を創り出し利用したのだ。怒りは無意識の感情ではない。認識して利用するのだ。
22.「よくできたね」とほめるのではない。「ありがとう、助かったよ」と感謝を伝えるのだ。
23.大切なことは「共感」することだ。
「大切なのは共感することだ。共感とは、相手の目で見、相手の耳で聞き、相手の心で感じることである」
24.人間は自分の人生を描く画家である。 あなたを作ったのはあなた。 これからの人生を決めるのもあなた。
25.健全な人は、相手を変えようとせず自分がかわる。不健全な人は、相手を操作し、変えようとする。
26.「やる気がなくなった」のではない。 「やる気をなくす」という決断を自分でしただけだ。
27.あなたが出来ない理由は、環境を言い訳にして「努力から逃げている」から。
28.人はあらゆる手を使って自分を重要人物だと思わせたい(世話を焼くことも、リストカットも)
29.人は「注目を集めたい」だめなら「力を示す」だめなら「復讐する」だめなら「回避する」
30.感情は「相手を操作・支配するため」と「自分自身を突き動かすため」に利用される。
31.「感情に支配される」のではなく、「背中押し」又は「ブレーキ」のために感情を利用すること。
32.自分でやると失敗するかもしれないから誰かにやってほしい、と思う人は社会的に孤立する。
33.「相手」は誰で、「目的」は何か?を推測しながら相手を観察する。
34.「理性と感情」「意識と無意識」は対立しない。同じ目標に向かって補い合っている。
35.子供は親の愛や関心を引くために戦略を実行している。それが性格となる。
36.0歳から10歳までの家族の、関係図、人間関係、雰囲気、共有された価値、がその人の性格を形作る。
37.相手の問題行動を直すには、共に信頼関係を築いてしばらく経ってから自分がどう考えるかを伝えること。
38.問題行動を叱ると、注目することになる。だから相手はやめない。だから正しい行動のみに注目する。
39.強制を辞める。相手に自分で決めさせる。自分を信じ他人を信じ居場所を見つける。
40.他人の評価を気にする人は自分のことばかり考えている人。つまり勇気がない人。
41.誰からもほめられず認められなくても自分が相手に貢献できていることそのものに満足すること。
42.出来ている部分に着目して感謝する。
43.共感とは「相手の置かれている状況や考え方、意図、感情、関心などに関心をもつこと」
44.「怒り」は「さみしさ」「悔しさ」「悲しさ」が先にあり、それが相手に理解してもらえないときに「怒る」
45.原因究明はせず、分析もせず、いきなり「こんなやり方はどうかな?」と提案する。
46.あらゆる人間関係のトラブル原因は他人の課題に土足で踏み込む、から。
47.自分の課題とは「その問題を放置した場合、不利益を被るのは誰か?」で考える。
48.自分と他者との「課題の分離」が出来るようになるとシアワセの第一歩である。
砂川よしひろ(沖縄県浦添市在)
教育アドバイサー 子育て・学習支援
企画編集者(自分史 地域史 社史の制作)
コピーライティング 人生コーチング
090-4981-8723 sunayoshi222@softbank.ne.jp
2016年03月31日
人生に革命が起きる アドラー名言集98
数時間かけてネットで調べて取り出しまとめてみました。
アルフレッド・アドラー(1870年2月7日~1937年5月28日)は、オーストリア出身の精神科医、心理学者、社会理論家。ジークムント・フロイトおよびカール・グスタフ・ユングと並んで現代のパーソナリティ理論や心理療法を確立した1人。
アドラーについては、初期の頃のフロイトとの関わりについて誤解があるが、アドラーはフロイトの共同研究者であり、1911年にはフロイトのグループとは完全に決別し、個人心理学(アドラー心理学)を創始した。
人生に革命が起きる98の言葉
1.世話好きな人は、単に優しい人なのではない。相手を自分に依存させ、自分が重要な人であることを実感したいのだ。
2.かまってほしい場合の4つの行動パターン
①注目を集める:注意を引いたり、要求したりする。
②力を示す:かんしゃくを起したり、怒りをぶつけたり、泣いたりする。
③復讐:問題行動を起し、相手に不快感を与える。家事放棄や非行に走ったりする。
④回避:あきらめて努力しなくなる。課題から逃れたり自分の弱さや落ち込みをひけらかす。
3.悲しいから涙を流すのではない。相手を責め、同情や注目を引くために泣いているのだ。
4.カッときて自分を見失い怒鳴ったのではない。相手を支配するために、怒りという感情を創り出し利用したのだ。
5.子供は感情でしか大人を支配できない。大人になってからも感情を使って人を動かそうとするのは、幼稚である。
6.人はライフスタイル(=性格)を10歳くらいまでに自分で決めて完成させる。そして、それを一生使い続けるのだ。
7.幸福な人生を歩む人のライフスタイル(=性格)は、必ずコモンセンス(=共通感覚)と一致している。
8.子供にとって家族は「世界そのもの」であり、親から愛されなければ生きていけない。そのための命がけの戦略が、そのまま性格の形成につながるのだ。
9.叱られたり、ほめられたりして育った人は、叱られたり、ほめられたりしないと行動しなくなる。そして、評価してくれない相手を、敵だと思うようになるのだ。
10.「よくできたね」とほめるのではない。「ありがとう、助かったよ」と感謝を伝えるのだ。感謝される喜びを体験すれば、自ら進んで貢献を繰り返すだろう。
11.判断に迷った時は、より大きな集団の利益を優先することだ。自分よりも仲間たち。仲間たちよりも社会全体。そうすれば判断を間違うことはないだろう。
12.行動に問題があるとしても、その背後にある動機や目的は、必ずや「善」である。
13.すべての悩みは対人関係の課題である。仙人のような世捨て人でさえも、実は他人の目を気にしているのだ。
14.人生には3つの課題がある。1つ目は「仕事の課題」。2つ目は「交友の課題」。3つ目は「愛の課題」である。そして後の方になるほど解決は難しくなる。
15.愛の課題とは、異性とのつきあいや夫婦関係のことである。人生で一番困難な課題であるがゆえに、解決できれば深いやすらぎが訪れるだろう。
16.それが「あなたの課題」ならば、たとえ親に反対されても従う必要はない。自分の課題に足を踏み込ませてはいけないのだ。
17.「暗い」のではなく「優しい」のだ。「のろま」ではなく「ていねい」なのだ。「失敗ばかり」ではなく「たくさんのチャレンジをしている」のだ。
18.ほめてはいけない。ほめることは「あなたは私よりも下の存在だ」「どうせあなたにはできっこない」と相手に伝えることに等しいからだ
19.「信用」するのではなく「信頼」するのだ。「信頼」とは裏付けも担保もなく相手を信じること。裏切られる可能性があっても相手を信じるのである。
20.自分の不完全さを認め、受け容れなさい。相手の不完全さを認め、許しなさい。
21.苦しみから抜け出す方法はたった一つ。他の人を喜ばせることだ。「自分に何ができるか」を考え、それを実行すればよい。
22.仕事で敗北しませんでした。働かなかったからです。人間関係で失敗しませんでした。人の輪に入らなかったからです。彼の人生は完全で、そして最悪だった。
23.誰かが始めなくてはならない。見返りが一切なくても、誰も認めてくれなくても、「あなたから」始めるのだ。
24.「この子は言葉を覚えるのが遅いので・・・・・・」と母親が子どもの通訳を買って出る。すると子どもは、自分で話す必要がなくなり、本当に言葉が遅くなるだろう。
25.罰を与えるのではない。結末を体験させるのだ。子どもが食事の時間になっても帰ってこなければ、一切叱らずに食事を出さなければよい。
26.問題行動に注目すると人はその問題行動を繰り返す。叱ることは、悪い習慣を身につけさせる最高のトレーニングなのだ。
27.叱られたり、ほめられたりして育った人は、叱られたりほめられたりしないと行動をしなくなる。そして、評価してくれない相手を敵だと思うようになるのだ。
28.あなたのために他人がいるわけではない。「〇〇してくれない」という悩みは、自分のことしか考えていない何よりの証拠である。
29.すべての悩みは対人関係の課題である。仙人のような世捨て人でさえも、実は他人の目を気にしているのだ。
30.自ら変わりたいと思い努力をすれば、ライフスタイル(性格)を変えることは十分に可能だ。性格は死ぬ1~2日前まで変えられる。
31.ライフスタイル(性格)とは人生の設計図であり、人生という舞台の脚本である。ライフスタイルが変われば、人生がガラリと変わるだろう。
32.人生が困難なのではない。あなたが人生を困難にしているのだ。
「現在の人生を決めているのは「運命」や「過去」のトラウマではなく、自分自身の考えかたである、ということです。だからこそ、私たちは、いつでも決意さえすれば、自分の人生をシンプルにすることができるのです」
33.遺伝や育った環境は単なる「材料」でしかない.。引っ込み思案になる、という方法を自らが選択したのだ。
35.「変われない」のではない。「変わらない」という決断を自分でしているだけだ
36.相手を「支配」するために「怒り」という感情を創り出し利用したのだ。怒りは無意識の感情ではない。認識して利用するのだ。
37.性格は死ぬ1〜2日前まで変えられる
表層的な性格表現だけではなく、自らの中核にある「自己概念」「世界像」「自己理想」を明確にしていくのだ。
38.「よくできたね」とほめるのではない。「ありがとう、助かったよ」と感謝を伝えるのだ。
「ほめる」と「感謝する」は明らかに違う。
39.自分の不完全さを認め、受け容れなさい。相手の不完全さを認め、許しなさい
40.大切なことは「共感」することだ。
「大切なのは共感することだ。共感とは、相手の目で見、相手の耳で聞き、相手の心で感じることである」
41.陰口を言われても、嫌われても、あなたが気にすることはない。「相手があなたをどう感じるか」は相手の課題なのだから
「私たちが他人の感情や行動をコントロールすることはできません。できないことをしようとするから苦しいのです。相手の課題に踏み込まず、自分の課題に相手を踏み込ませなければいいのです」
42.人間は自分の人生を描く画家である。 あなたを作ったのはあなた。 これからの人生を決めるのもあなた。
現在の人生を決めているのは「運命」や「過去」のトラウマではなく自分自身の考え方であると思い、未来から今を見ることを習慣にするだけでよいのです。
43.人は過去に縛られているわけではない。あなたの描く未来があなたを規定しているのだ。過去の原因は「解説」になっても「解決」にはならないだろう。
44.健全な人は、相手を変えようとせず自分がかわる。不健全な人は、相手を操作し、変えようとする。
45.「やる気がなくなった」のではない。 「やる気をなくす」という決断を自分でしただけだ。
46.できない自分を責めている限り、永遠に幸せにはなれないだろう。
47.自分だけでなく、仲間の利益を大切にすること。受け取るよりも多く、相手に与えること。幸福になる唯一の道である。
48.刺激⇒反応 ではなく、刺激 ⇒ 認知(して意味づける)⇒ 反応。
49.あなたが出来ない理由は、環境を言い訳にして「努力から逃げている」から。
50.人はあらゆる手を使って自分を重要人物だと思わせたい(世話を焼くことも、リストカットも)
51.人は「注目を集めたい」だめなら「力を示す」だめなら「復讐する」だめなら「回避する」
52.感情は「相手を操作・支配するため」と「自分自身を突き動かすため」に利用される。
53.「感情に支配される」のではなく、「背中押し」又は「ブレーキ」のために感情を利用すること。
54.自分でやると失敗するかもしれないから誰かにやってほしい、と思う人は社会的に孤立する。
55.「相手」は誰で、「目的」は何か?を推測しながら相手を観察する。
56.「理性と感情」「意識と無意識」は対立しない。同じ目標に向かって補い合っている。
57.感情は性格から出てくる「排泄物」。「排泄物」は変えられないから、その前段階の「認知」を修正する。修正するにはその前段階の性格を変える。
58.性格は、どのように行動すればうまくいくか、という信念である。自分で決めたものである。
59「私は○○である」「世の中の人々は○○である」「私は○○であらねばならない」この3つが性格の根っこである。
60.性格を変える、とは、精神的な所有物を変えることではなく、その使用法を変える事である。
61.全ての悩みは対人関係の課題である。「自分はどのような人間でありたいか」と考える時、他人の目がある。
62.仕事の課題<交友の課題<愛の課題の順番で難しくなる(人生の課題)
63.結婚は「相手が間違っている」「相手を教育する」と思っていては失敗する。「相互に与えあう」平等な関係でないと失敗する。
64.子供は親の愛や関心を引くために戦略を実行している。それが性格となる。
65.0歳から10歳までの家族の、関係図、人間関係、雰囲気、共有された価値、がその人の性格を形作る。
66.相手の問題行動を直すには、共に信頼関係を築いてしばらく経ってから自分がどう考えるかを伝えること。
67.問題行動を叱ると、注目することになる。だから相手はやめない。だから正しい行動のみに注目する。
68.他人と比較しない。自信を失う。たとえわずかでも出来ていることを認めさらに増やすように要望する。
69.結末を体験させる。失敗させて学ばせる。自ら変わろうと決断させる。任せるから出来るようになる。
70.罰を与えるのではなく、結末を体験させ、気付かせる。
71.教育とは相手が一人で課題を解決できるようにすること。
72.人の育て方に迷った時は「この体験を通じて相手は何を学ぶだろうか?」と考える。
73.「居場所」を作る。他者へ貢献すると、他者から感謝され他者からお返しとして支援される。すると居場所ができる
74.誰かが始めなてくてはならない。見返りがなくても認められなくても、あなたから始める。
75.人生における、あらゆる失敗の原因は自分のことしか考えていないことにある。
76.「他者は私を援助してくれる」「私は他者に貢献できる」「私には居場所がある」
77.居場所が無いと感じると病んだり溺れたりする。他者に貢献せよ。
78.シアワセは人間関係でしか感じられない。「勇気」と「共同体感覚」
79.仕事の課題は「顧客」交友の課題は「友人」、との「信頼と貢献」です。
80.強制を辞める。相手に自分で決めさせる。自分を信じ他人を信じ居場所を見つける。
81.苦しみから抜け出すには、「他の人を喜ばせる」。そして感謝の言葉をもらう。すると居場所が出来て、抜けだせる。
82.違う意見は当たり前。違うからこそ意味がある。違いを容認すると共同体感覚が向上して居場所が見つかる。
83.不完全でいい。だからこそ人間臭い。だからこそ愛らしい。
84.「自分は役立っている」と実感するのに他者評価は不要。自己満足で良い。
85.判断に迷ったらより大きな集団の利益を優先する。
86.困難(仕事、交友、愛)が来ても「相手を思い、優先」できるか。これを克服する力が「勇気」
87.他人の評価を気にする人は自分のことばかり考えている人。つまり勇気がない人。
88.誰からもほめられず認められなくても自分が相手に貢献できていることそのものに満足すること。
89.能力不足と相手の価値とは何の関係もない。
90.問題の原因究明はダメだし。「解決法」と「可能性」に集中すべき。
91.出来ている部分に着目して感謝する。
92.共感とは「相手の置かれている状況や考え方、意図、感情、関心などに関心をもつこと」
93.相手にyes・noの選択の余地がある問いかけにするだけで相手は「尊重されている」と思う。
94.「怒り」は「さみしさ」「悔しさ」「悲しさ」が先にあり、それが相手に理解してもらえないときに「怒る」
95.原因究明はせず、分析もせず、いきなり「こんなやり方はどうかな?」と提案する。
96.あらゆる人間関係のトラブル原因は他人の課題に土足で踏み込む、から。
97.自分の課題とは「その問題を放置した場合、不利益を被るのは誰か?」で考える。
98.自分と他者との「課題の分離」が出来るようになるとシアワセの第一歩である。
砂川よしひろ(沖縄県浦添市在)
教育アドバイサー 子育て・学習支援
企画編集者(自分史 地域史 社史の制作)
コピーライティング 人生コーチング
090-4981-8723 sunayoshi222@softbank.ne.jp
アルフレッド・アドラー(1870年2月7日~1937年5月28日)は、オーストリア出身の精神科医、心理学者、社会理論家。ジークムント・フロイトおよびカール・グスタフ・ユングと並んで現代のパーソナリティ理論や心理療法を確立した1人。
アドラーについては、初期の頃のフロイトとの関わりについて誤解があるが、アドラーはフロイトの共同研究者であり、1911年にはフロイトのグループとは完全に決別し、個人心理学(アドラー心理学)を創始した。
人生に革命が起きる98の言葉
1.世話好きな人は、単に優しい人なのではない。相手を自分に依存させ、自分が重要な人であることを実感したいのだ。
2.かまってほしい場合の4つの行動パターン
①注目を集める:注意を引いたり、要求したりする。
②力を示す:かんしゃくを起したり、怒りをぶつけたり、泣いたりする。
③復讐:問題行動を起し、相手に不快感を与える。家事放棄や非行に走ったりする。
④回避:あきらめて努力しなくなる。課題から逃れたり自分の弱さや落ち込みをひけらかす。
3.悲しいから涙を流すのではない。相手を責め、同情や注目を引くために泣いているのだ。
4.カッときて自分を見失い怒鳴ったのではない。相手を支配するために、怒りという感情を創り出し利用したのだ。
5.子供は感情でしか大人を支配できない。大人になってからも感情を使って人を動かそうとするのは、幼稚である。
6.人はライフスタイル(=性格)を10歳くらいまでに自分で決めて完成させる。そして、それを一生使い続けるのだ。
7.幸福な人生を歩む人のライフスタイル(=性格)は、必ずコモンセンス(=共通感覚)と一致している。
8.子供にとって家族は「世界そのもの」であり、親から愛されなければ生きていけない。そのための命がけの戦略が、そのまま性格の形成につながるのだ。
9.叱られたり、ほめられたりして育った人は、叱られたり、ほめられたりしないと行動しなくなる。そして、評価してくれない相手を、敵だと思うようになるのだ。
10.「よくできたね」とほめるのではない。「ありがとう、助かったよ」と感謝を伝えるのだ。感謝される喜びを体験すれば、自ら進んで貢献を繰り返すだろう。
11.判断に迷った時は、より大きな集団の利益を優先することだ。自分よりも仲間たち。仲間たちよりも社会全体。そうすれば判断を間違うことはないだろう。
12.行動に問題があるとしても、その背後にある動機や目的は、必ずや「善」である。
13.すべての悩みは対人関係の課題である。仙人のような世捨て人でさえも、実は他人の目を気にしているのだ。
14.人生には3つの課題がある。1つ目は「仕事の課題」。2つ目は「交友の課題」。3つ目は「愛の課題」である。そして後の方になるほど解決は難しくなる。
15.愛の課題とは、異性とのつきあいや夫婦関係のことである。人生で一番困難な課題であるがゆえに、解決できれば深いやすらぎが訪れるだろう。
16.それが「あなたの課題」ならば、たとえ親に反対されても従う必要はない。自分の課題に足を踏み込ませてはいけないのだ。
17.「暗い」のではなく「優しい」のだ。「のろま」ではなく「ていねい」なのだ。「失敗ばかり」ではなく「たくさんのチャレンジをしている」のだ。
18.ほめてはいけない。ほめることは「あなたは私よりも下の存在だ」「どうせあなたにはできっこない」と相手に伝えることに等しいからだ
19.「信用」するのではなく「信頼」するのだ。「信頼」とは裏付けも担保もなく相手を信じること。裏切られる可能性があっても相手を信じるのである。
20.自分の不完全さを認め、受け容れなさい。相手の不完全さを認め、許しなさい。
21.苦しみから抜け出す方法はたった一つ。他の人を喜ばせることだ。「自分に何ができるか」を考え、それを実行すればよい。
22.仕事で敗北しませんでした。働かなかったからです。人間関係で失敗しませんでした。人の輪に入らなかったからです。彼の人生は完全で、そして最悪だった。
23.誰かが始めなくてはならない。見返りが一切なくても、誰も認めてくれなくても、「あなたから」始めるのだ。
24.「この子は言葉を覚えるのが遅いので・・・・・・」と母親が子どもの通訳を買って出る。すると子どもは、自分で話す必要がなくなり、本当に言葉が遅くなるだろう。
25.罰を与えるのではない。結末を体験させるのだ。子どもが食事の時間になっても帰ってこなければ、一切叱らずに食事を出さなければよい。
26.問題行動に注目すると人はその問題行動を繰り返す。叱ることは、悪い習慣を身につけさせる最高のトレーニングなのだ。
27.叱られたり、ほめられたりして育った人は、叱られたりほめられたりしないと行動をしなくなる。そして、評価してくれない相手を敵だと思うようになるのだ。
28.あなたのために他人がいるわけではない。「〇〇してくれない」という悩みは、自分のことしか考えていない何よりの証拠である。
29.すべての悩みは対人関係の課題である。仙人のような世捨て人でさえも、実は他人の目を気にしているのだ。
30.自ら変わりたいと思い努力をすれば、ライフスタイル(性格)を変えることは十分に可能だ。性格は死ぬ1~2日前まで変えられる。
31.ライフスタイル(性格)とは人生の設計図であり、人生という舞台の脚本である。ライフスタイルが変われば、人生がガラリと変わるだろう。
32.人生が困難なのではない。あなたが人生を困難にしているのだ。
「現在の人生を決めているのは「運命」や「過去」のトラウマではなく、自分自身の考えかたである、ということです。だからこそ、私たちは、いつでも決意さえすれば、自分の人生をシンプルにすることができるのです」
33.遺伝や育った環境は単なる「材料」でしかない.。引っ込み思案になる、という方法を自らが選択したのだ。
35.「変われない」のではない。「変わらない」という決断を自分でしているだけだ
36.相手を「支配」するために「怒り」という感情を創り出し利用したのだ。怒りは無意識の感情ではない。認識して利用するのだ。
37.性格は死ぬ1〜2日前まで変えられる
表層的な性格表現だけではなく、自らの中核にある「自己概念」「世界像」「自己理想」を明確にしていくのだ。
38.「よくできたね」とほめるのではない。「ありがとう、助かったよ」と感謝を伝えるのだ。
「ほめる」と「感謝する」は明らかに違う。
39.自分の不完全さを認め、受け容れなさい。相手の不完全さを認め、許しなさい
40.大切なことは「共感」することだ。
「大切なのは共感することだ。共感とは、相手の目で見、相手の耳で聞き、相手の心で感じることである」
41.陰口を言われても、嫌われても、あなたが気にすることはない。「相手があなたをどう感じるか」は相手の課題なのだから
「私たちが他人の感情や行動をコントロールすることはできません。できないことをしようとするから苦しいのです。相手の課題に踏み込まず、自分の課題に相手を踏み込ませなければいいのです」
42.人間は自分の人生を描く画家である。 あなたを作ったのはあなた。 これからの人生を決めるのもあなた。
現在の人生を決めているのは「運命」や「過去」のトラウマではなく自分自身の考え方であると思い、未来から今を見ることを習慣にするだけでよいのです。
43.人は過去に縛られているわけではない。あなたの描く未来があなたを規定しているのだ。過去の原因は「解説」になっても「解決」にはならないだろう。
44.健全な人は、相手を変えようとせず自分がかわる。不健全な人は、相手を操作し、変えようとする。
45.「やる気がなくなった」のではない。 「やる気をなくす」という決断を自分でしただけだ。
46.できない自分を責めている限り、永遠に幸せにはなれないだろう。
47.自分だけでなく、仲間の利益を大切にすること。受け取るよりも多く、相手に与えること。幸福になる唯一の道である。
48.刺激⇒反応 ではなく、刺激 ⇒ 認知(して意味づける)⇒ 反応。
49.あなたが出来ない理由は、環境を言い訳にして「努力から逃げている」から。
50.人はあらゆる手を使って自分を重要人物だと思わせたい(世話を焼くことも、リストカットも)
51.人は「注目を集めたい」だめなら「力を示す」だめなら「復讐する」だめなら「回避する」
52.感情は「相手を操作・支配するため」と「自分自身を突き動かすため」に利用される。
53.「感情に支配される」のではなく、「背中押し」又は「ブレーキ」のために感情を利用すること。
54.自分でやると失敗するかもしれないから誰かにやってほしい、と思う人は社会的に孤立する。
55.「相手」は誰で、「目的」は何か?を推測しながら相手を観察する。
56.「理性と感情」「意識と無意識」は対立しない。同じ目標に向かって補い合っている。
57.感情は性格から出てくる「排泄物」。「排泄物」は変えられないから、その前段階の「認知」を修正する。修正するにはその前段階の性格を変える。
58.性格は、どのように行動すればうまくいくか、という信念である。自分で決めたものである。
59「私は○○である」「世の中の人々は○○である」「私は○○であらねばならない」この3つが性格の根っこである。
60.性格を変える、とは、精神的な所有物を変えることではなく、その使用法を変える事である。
61.全ての悩みは対人関係の課題である。「自分はどのような人間でありたいか」と考える時、他人の目がある。
62.仕事の課題<交友の課題<愛の課題の順番で難しくなる(人生の課題)
63.結婚は「相手が間違っている」「相手を教育する」と思っていては失敗する。「相互に与えあう」平等な関係でないと失敗する。
64.子供は親の愛や関心を引くために戦略を実行している。それが性格となる。
65.0歳から10歳までの家族の、関係図、人間関係、雰囲気、共有された価値、がその人の性格を形作る。
66.相手の問題行動を直すには、共に信頼関係を築いてしばらく経ってから自分がどう考えるかを伝えること。
67.問題行動を叱ると、注目することになる。だから相手はやめない。だから正しい行動のみに注目する。
68.他人と比較しない。自信を失う。たとえわずかでも出来ていることを認めさらに増やすように要望する。
69.結末を体験させる。失敗させて学ばせる。自ら変わろうと決断させる。任せるから出来るようになる。
70.罰を与えるのではなく、結末を体験させ、気付かせる。
71.教育とは相手が一人で課題を解決できるようにすること。
72.人の育て方に迷った時は「この体験を通じて相手は何を学ぶだろうか?」と考える。
73.「居場所」を作る。他者へ貢献すると、他者から感謝され他者からお返しとして支援される。すると居場所ができる
74.誰かが始めなてくてはならない。見返りがなくても認められなくても、あなたから始める。
75.人生における、あらゆる失敗の原因は自分のことしか考えていないことにある。
76.「他者は私を援助してくれる」「私は他者に貢献できる」「私には居場所がある」
77.居場所が無いと感じると病んだり溺れたりする。他者に貢献せよ。
78.シアワセは人間関係でしか感じられない。「勇気」と「共同体感覚」
79.仕事の課題は「顧客」交友の課題は「友人」、との「信頼と貢献」です。
80.強制を辞める。相手に自分で決めさせる。自分を信じ他人を信じ居場所を見つける。
81.苦しみから抜け出すには、「他の人を喜ばせる」。そして感謝の言葉をもらう。すると居場所が出来て、抜けだせる。
82.違う意見は当たり前。違うからこそ意味がある。違いを容認すると共同体感覚が向上して居場所が見つかる。
83.不完全でいい。だからこそ人間臭い。だからこそ愛らしい。
84.「自分は役立っている」と実感するのに他者評価は不要。自己満足で良い。
85.判断に迷ったらより大きな集団の利益を優先する。
86.困難(仕事、交友、愛)が来ても「相手を思い、優先」できるか。これを克服する力が「勇気」
87.他人の評価を気にする人は自分のことばかり考えている人。つまり勇気がない人。
88.誰からもほめられず認められなくても自分が相手に貢献できていることそのものに満足すること。
89.能力不足と相手の価値とは何の関係もない。
90.問題の原因究明はダメだし。「解決法」と「可能性」に集中すべき。
91.出来ている部分に着目して感謝する。
92.共感とは「相手の置かれている状況や考え方、意図、感情、関心などに関心をもつこと」
93.相手にyes・noの選択の余地がある問いかけにするだけで相手は「尊重されている」と思う。
94.「怒り」は「さみしさ」「悔しさ」「悲しさ」が先にあり、それが相手に理解してもらえないときに「怒る」
95.原因究明はせず、分析もせず、いきなり「こんなやり方はどうかな?」と提案する。
96.あらゆる人間関係のトラブル原因は他人の課題に土足で踏み込む、から。
97.自分の課題とは「その問題を放置した場合、不利益を被るのは誰か?」で考える。
98.自分と他者との「課題の分離」が出来るようになるとシアワセの第一歩である。
砂川よしひろ(沖縄県浦添市在)
教育アドバイサー 子育て・学習支援
企画編集者(自分史 地域史 社史の制作)
コピーライティング 人生コーチング
090-4981-8723 sunayoshi222@softbank.ne.jp